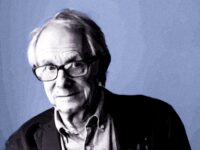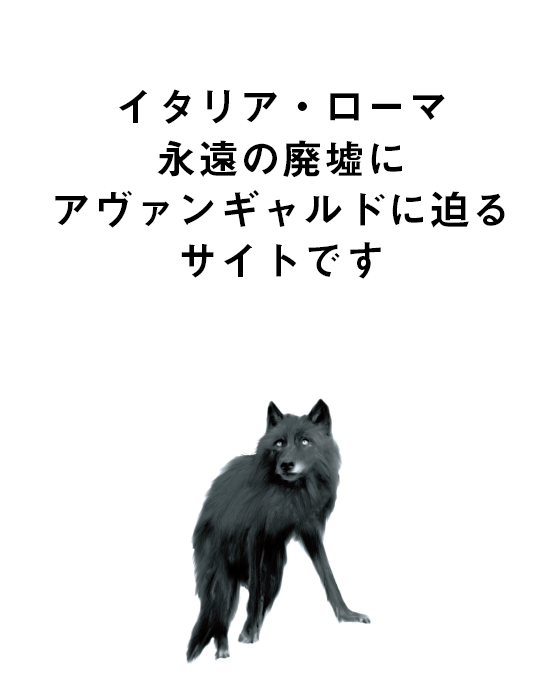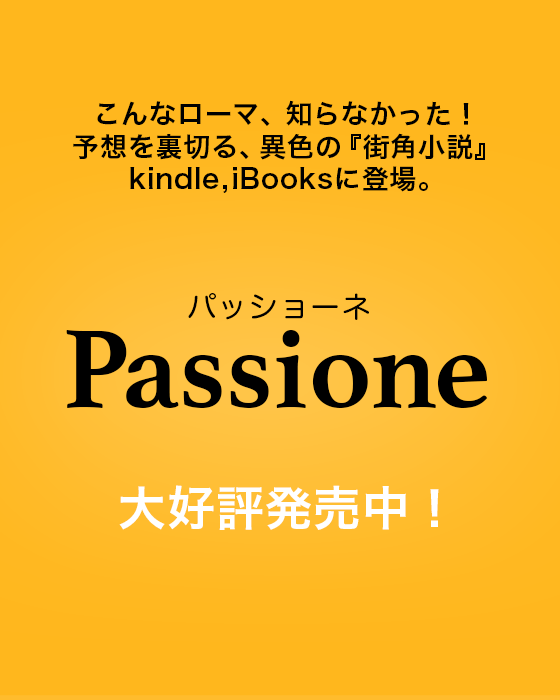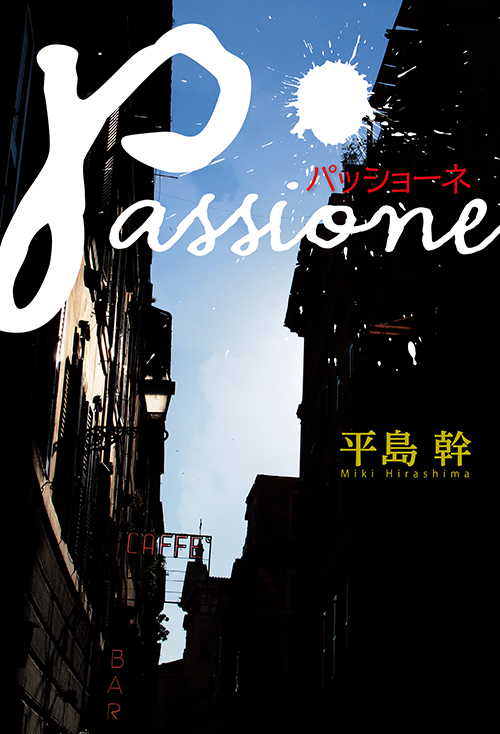ヴァレンティーノ・ザイケンは、イタリアの現代詩における重要な詩人のひとり、と同時にUn personaggio(ペルソナッジョ)としても名高い人物です。イタリア語の辞書で「Personaggio」という単語をひくと、①重要な人物、著名人、名士 ②(劇、小説の)登場人物 ③変わり者、特異な人物、という3つの意味が現れますが、ザイケンに関して言えば、そのすべての意味があてはまると言ってもよいでしょう。
ザイケンのような人物に出会うと、「ローマという街の懐は底なしに深い。こんなに強烈な個性をも難なく飲み込んで街の風景にしてしまうとは」と素直に思います。何より彼は、石を投げれば「詩人」に当たる、とも言われるローマの街に群れ遊ぶ「詩人もどき」の人々とは次元を異にする、正真正銘の職業詩人なのです。60年初頭、若き詩人としてローマの街に忽然と現れ、かのアルベルト・モラヴィアをして「ローマの街にネオ・マルツィアーレ(Neo Marziale*)が現れた」と賞賛させたという逸話を持つ人物でもあります。今までに通算11冊の詩集を出版(アンソロジーを含めると12冊)。そのほか戯曲、ラジオドラマ、翻訳、批評を数多く発表していますが、現在もその創作の勢いはとどまることなく、コンスタントに新作が発表され、去年の暮れには初の小説「La Sumera(ラ・スメラ)」が出版されたばかりです。
*Marco Valerio Marzialeは古代ローマ時代、その時代の風俗をラテン語でエピグラム(警告、寸鉄詩として残した)として書いた詩人。15冊の詩集、1561の詩篇が残っている。
ご本人は、「知的であることなんて、最もくだらないことだよ。僕は合理性、秩序などは大嫌い。馬鹿馬鹿しいじゃないか」と言い続けるにも関わらず、その詩の数々は、ローマの芸術、文芸界のアカデミックな権威、Intellettualità(知性)の代表である人物たちの関心を集めてやまず、たとえばアキーレ・ボニート・オリーヴァ、レナート・ニコリーニ、フランコ・プリーニ、そしてアカデミア・ディ・サン・ルカのディレクター、フランチェスコ・モスキーニ、パオロ・ポルトゲージ、ジュリオ・フェローニなどなど、美術、建築、文学界のローマの名だたる批評家たちを、毎回唸らせるのです。
実際、ザイケンの詩、小説というのは、まったく凡庸ではありません。本質的でありながらありきたりでない、軽く、すばやい言葉で表現され、非常に繊細なセンスのユーモア、アイロニーがちりばめられている。読むうちにクスリと笑いがこみ上げる、ちょっとした棘のあるユーモア、辛辣な批評も見え隠れしますが、それは決して何かを(あるいは何者かを)馬鹿にしたり、侮る笑いではなく、いわば人間という「存在」(非存在も含め)そのものの、本質的な馬鹿馬鹿しさを再確認するような、奥行きのあるユーモアであり、辛辣さです。自身をも含めるあらゆるすべての「存在」そのものを、ザイケンはいつもどこかふざけながら言葉に焼きつけていく。例えば歴史家、文芸批評家のジュリオ・フェローニは、ザイケンのアイロニー、ユーモアは、たとえば「ゼノンのパラドックス」のようなものだ、と言っています。
スレンダーで頑健、きわめて姿勢がよい。いつもきちんとした身なりで礼儀正しく、厳しい眼差し。それなのに、ちょっとした瞬間、とぼけたオーラを漂わす詩人です。よく通るその声を決して荒げることなく、また自分を演出することもなく、それでいて、どのシーンでも自ずと注目を集め「あ、ヴァレンティーノ・ザイケンだ」とひときわ目立ち、少しもひっそりしていない。「詩人」という言葉がイメージさせる、感傷的でデカダン、憂鬱が渦巻く雰囲気とも程遠く、自ら課した人生のディシップリンを守り抜くという、硬質なエネルギーを放ってもいる。
この詩人はトリオンファーレ市場の、どの屋台が新鮮で味のいい野菜を売るか、どの肉屋が質のよい肉を、適正価格で売るか、綿密にリサーチもしてもいるし、料理を含む家事、家を修復などの大工仕事もプロはだしです。そして市場で買い物をしていても、料理をしていても、彼のその視線には彼の詩と同じアイロニーが満ち、一挙一動に、そこはかとした詩情が溢れている、と言っておきましょう。「ヴァレンティーノは彼自身の身体的行動そのものが表現するままの詩人である」とフェローニが言うように、彼の人生と彼の書く詩の宇宙はもはや同化しているのかもしれません。
さらに、Un personaggioとして、ザイケンの名を轟かせる由縁として、忘れてはならないのが、彼が住む「バラックの家」です。しかも、いまどき郊外や田舎街でも探すのが難しい、時代がかった風情を醸すそのバラックは、観光客とファッショナブルな人々で溢れるポポロ広場から歩いて5分の場所にある。ボルゲーゼ公園の森の裏、入り組んだ路地に異次元のように現れ、「ローマの中心街にこんな家があるなんて」と、訪れた人々をあっと驚かします。
「ローマの中心地にこっそりとあるバラックの家に孤りで住んでいる詩人」だなんて、あまりに出来すぎていて、ロマンティックに演出されているみたいだ、とは言いますまい。というのも、ザイケンはもう45年余り、この違法建築のバラックに「必然」が命じるまま、住んでいるに他ならず、引っ越す機会にも巡り合わなかっただけの話です。時を経て、この、ローマの最も賑やかな街角のすぐ側にあるバラックは、この詩人を語る際の、もはや「神話」ともなり、バラックが「ザイケンとその詩」のシンボルであり、また「ザイケンとその詩」がバラックのシンボルともなり、詩人とその家は次第に融合、一体化していきました。
この、高い壁に囲まれ、グリーンに塗られた頑丈な鉄柵の扉に守られたバラックは、そもそもは戦後、その地区に違法に建築された集合住宅の一角だったのだそうです。当時は近所で手工業を営む職人たちが住んでいたのですが、その職人たちが立ち去った70年代、ボヘミアンなアーティストたちが集団で移り住み、ザイケンもそのボヘミアンのひとりとしてやってきています。やがて時が経ち、友人たちがそれぞれに立ち去っていっても、ザイケンは友人の画家が住んでいた家の一角も譲り受け、その違法住宅に住み続けました。もちろん違法ですから、住みはじめた時から現在まで、ローマ市当局は「即刻立ち退き命令」を突きつけ、絶え間なく脅迫し続けていますが、イタリアの詩壇で重要なポストを占めるこの詩人は、頑として立ち退きません。
もはや家そのものが「天然自然」、という趣すら漂わせているザイケンのバラックに、はじめて訪れた際、その質素で無作為な佇まいが放つ「いい加減(よい意味で)」にわたしは衝撃を受けました。壁は朽ち、窓枠のペンキははげ落ちて、そこには詩人の時間、人生の、それこそ「いい加減(よい意味で)」な物語ひとつひとつがしっかりと刻み込まれている。無駄な家具はもちろん、飾りひとつなく、すべて詩人の手作りか、どこかの道で拾ってきたものが無秩序ながら調和を保って在るのです。その場所には詩人に似合わないものは何ひとつありません。友人たちが運良く招かれて、「ザイケンに招待された」と興奮し、得意になって自慢する、有名な「バラックの日曜の昼食会」が開かれる狭い庭には、少しも手入れされていない木々が、のびのびと生い茂り、冬場、ストーブに使う薪が、ドサッと無造作に転がっていました。
Fare della letteratura è spesso un modo di dissimulare le proprio frivolezza con l’ingegno della puerilità.(Valentino Zeichen : Aforismi )
文学をやるってことはたいてい、幼稚な素質から生まれる、それそのものの軽薄をいつわる方便である。
実を言うと、今回のヴァレンティーノ・ザイケンのロング・インタビューは、わたしの夢でもありました。遠い異国から訪れたわたしにとっては、ザイケンという詩人が、ローマという街の複雑な魅力を体現した人物に思えたからです。また、その詩に使われるボキャブラリーも詩人同様、まったくありふれていないのが、意欲をそそりました。外国人であるうえ、少し蛍光灯(LED時代には通用しない表現ですが)でもあるわたしには、彼の詩の数々に関して、辞書を片手にネットで調べながら何度も読んで、やっとその片鱗にたどりつける、という程度でも、どこかでパチッと言葉にハマった時は、あ、面白い、とこころ踊ります。また、よく通る声で朗々と、演劇的に朗読される彼の詩の会では、言葉が形づくる風景が蜃気楼のように浮かび上がる。
「僕には詩のマエストロー師匠ーというのがいない。言ってみれば自分自身が詩のマエストロ、ということでね。詩の何が面白いかというと、ありとあらゆる日常、シンプルなリアリティから文化、風俗、なにもかもを観察して、読者を冗談っぽくだましながら、違う世界へ連れ出すことだね。リアリティは詩の『種』みたいなものでー僕はリアリストというわけではないんだけれどねー詩を書くということは、今ここの現実とは違う、別次元のリアリティの地図をつくるチャンスってことでもあるんだよ」
「詩を書きはじめた頃は、自分はそもそも『感傷』というものがひどく苦手だったから、あれこれ思い悩んだんだけれどねーイタリアの詩壇では詩人は絶対的にシリアスでなくてはならず、ふざけすぎると抹殺されるからね(笑)。しかしあるとき、アイロニー、批判精神も『スタイル』になりうる、と確信したんだ。詩のスピリットというのは、inprevedebilita` (前もって見通すことのできない)、予想もつかないリアリティの再構築だ。僕はそれをきわめて早いスピードで、軽々と表現しようと思った。だから僕はアフォリズムや俳句など、エッセンシャルな要素だけで構成された詩のスタイルを好むんだ。それにだいいち、長い詩を書くっていうことは、くたびれることだから(笑)」
「僕は詩を書く前に演劇を学んでいたんだが、演劇と詩とは非常に近い位置にあると思っている。詩は演劇と同じように、そこにひとつのシーン、宇宙をつくりあげるだろう? 詩とはその宇宙で語られるモノローグのようなものかもしれない、とも思うんだ。少し前にテアトロ・アルジェンティーナで、Ciro di Peris(チロ・ディ・ペリス)の詩を朗読したんだけれどね。Ciro di Perisは600年代の詩人、僕の大好きな詩人なんだが、1600年代に書かれた彼の詩、言葉を、僕の声で物質化、つまり、誰もが体感できるようにした。紙に書かれた詩というものは『沈黙した』『声を持たない』『盲目』の言葉だが、誰かに読まれたり、声に出すことで、そのスピリットは蘇るんだよ。400年の間、声に出して読まれることのなかった、沈黙し続けたスピリットに僕の声を貸せたことは、興奮するような出来事だったね。僕の声が詩をフィジカルな波としたことで、彼の言葉、詩が空間に放たれたんだから。つまりこのように、書かれた言葉を読み、空間に放つ、という行為が、非常に演劇に近いと思うんだ」
さて、ザイケンのバラックにインタビューに行く前に、他のインタビューも読んでおこうと、新聞や雑誌の記事をいくつか読んでみると、いかにもザイケンらしいユーモアたっぷりのエピソードが語られていました。「詩」の世界を愛するインタビュアーの女性はローマの詩壇に心惹かれ、若い頃にイタリア北部から移り住んできたのだそうですが、その際、ザイケンに「たいして価値のないものには近づかないほうがいい。ローマには偽の詩人が大勢いるから注意しなさい」と忠告されたそうです。それから25年以上が経ったインタビューで、彼女が「やっと聞きたいことが聞けると思って、インタビューに来たんです。あのとき言っていた偽の詩人っていったい誰のことを言っていたんですか?」と尋ねると、「えっと、そんなこと言ったんなら、それは僕のことだよ!」ザイケンはケロリと答えていました。
若い頃から現在まで(多分)、恋多き詩人で、ウィットに富んだ恋愛の心情を描いた詩も少なくありません。少し前のインタビュー記事を読んでいると、ジャーナリストとのやりとりの途中、シリアスな詩作の話題から突如一転、「ところで、実は最近大きな恋愛が終わったところでね。とても消沈している。何もやる気がおこらない」とため息をついてもいた。「え? アモーレ? そうなんですか? それはまた一体どうして」と原因を追求されると「僕がいつまでも覚悟できないからだよ。彼女は僕の優柔不断に愛想をつかしたんだ。知っているだろう? 愛というものが人を殺すことだってあるってことを」とザイケンはしみじみ語っていました。そのときの彼は、すでに70歳をとっくに超えているはずですが、20代の青年のようなことをさらりと自然に言う、このような決して年をとらない詩人の有り様を、わたしはとても素敵だと思います。そのザイケンには、恋人が未婚のままに産んだ、ロンドンに住む美しい海洋学者の娘さんがいて、そういえば、かつて「詩の朗読会」にいらしているところを見かけたことがあリました。
さて、いよいよインタビューのアポイントメントを確認するために、その前日に電話をかけ、時間のコンファームをすることにしました。ところが電話に出たのは、息も絶え絶え、といった弱々しい声の老人。「どなた? はあ? ここには誰もいませんよ」おかしいな、電話番号を間違えたのかもしれない、と慌てます。「えっと、すみません。明日ザイケン氏にインタビューに伺おうと思っている者なのですが」と言うと、電話の主は、途端にエネルギーに満ち溢れた、よく通る声でカラカラと笑いました。「ごめん、ごめん、また携帯電話会社の押し売りかと思ったんだ。明日だろう? 11時はどうかな」
そういうわけで、少し緊張していたわたしも、気楽な気分でポポロ広場へと向かったわけです。