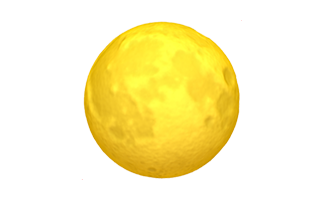Ⅶ
スパルタコは、あの不思議な花売りと出会った日からずっと考え続けた。
自分にかけられた理不尽な魔法のこと。狼として生きた十一回の生のこと。そして老いた現在の自分の境遇。ローマでのマテオとの17年の生活のこと。突然出会った魔術師と名乗る男の、脈絡のない話。それらをひたすらに考えた。そして、考えても、考えても、何ひとつ納得した結論には到達しなかった。
ここ数日の間、初夏だというのに吼えもせず、散歩に行ってもマテオの後をとぼとぼと力なく、いつも空ろな眼をしているスパルタコを、はじめマテオは、くたびれて機嫌が悪いのだろう、ぐらいにしか考えなかった。
「何でもない。すぐに良くなる」
力づけるようにスパルタコの背中を撫でていたが、
「スパルタコも、もういい加減な歳なんだぜ。そろそろお迎えが来たんじゃないのか」
友達から言われて慌てた。
「いや、大丈夫だ。スパルタコは不死身だ。まだまだ三十年は生きる。こいつは狼なんだからな。おい、スパルタコ、行くぞ。しっかり歩くんだ」
そうムキになって切り返し、力なく歩くスパルタコの手綱を無理やりぐいぐい引っ張った。
一週間が過ぎ、十日が過ぎ、それでもスパルタコが一向に元気にならないので、マテオは、ひょっとしたらこれは相当に深刻な事態なのかもしれない、と自らも深刻になってきた。悪い病気なのではないかと獣医に連れて行ったり、きっとごみごみした街の環境がよくないからだと、空気のいい田舎に連れて行ったり、せっかく仲良くなったアフリカの娘のことも忘れるほどに、スパルタコに懸かりきりになった。夜を遊び歩く悪友たちの誘いもきっぱり断った。
「あのマテオが、最近ずいぶん元気ないじゃないか。何? 犬の具合が悪いのかい? ほう、鬼の目に涙か。あんな憎らしい奴にも、そんな殊勝な心がけがあったなんて驚きだね。まあ、しばらくは、おとなしくしてるだろうから、我々は安泰だけれどね」
ろくに勘定は払わないくせに、このワインはコルク栓の匂いが滲みついていてまずい、代えてくれ、と必ずケチをつけ、閉店を過ぎてもなかなか帰らないマテオにてこずっていた、エノテカの親父はほっと胸を撫でおろした。
母親を早くに亡くし、そののち後妻をもらった父親とは音信普通。妹とも遠く離れて住むマテオにとっては、スパルタコだけが家族とも言えるものだった。共に過ごした17年間、マテオにはスパルタコのいない毎日など、もはや考えられなくなっていたのだ。
ある晩、マテオは力ないスパルタコのそばに座り込む。
「死ぬなよ。おまえは絶対に死んではならない。いや、おまえは死なない。おまえが死んだら僕が困る。どうすればいいんだ。僕はひとりになるのは嫌だ」
懇願するような声で呟いて、いよいよスパルタコを憂鬱にさせた。
刻々と約束の満月の夜は迫っている。スパルタコのあまりの覇気のなさに、老いたスパルタコの最後の時が今日明日にでも訪れるのではないか、と始終胸騒ぎがして、マテオは一刻も気が休まらない様子だった。一方スパルタコは、そんなマテオを気にしながらも、ただひたすらに自分に問い続けていたのだ。
庭師をしていた遠い昔のように、人間として生き直すことが、自分にとって本当に幸福なことなのか。自分は本当にそれを望んでいるのか。もしこのまま魔法に従うなら、自分はあと八回の生を獣として生きなければならないのだ。残忍な本能に翻弄され、血の匂いに飢えながら生きなければならない。今まで獣として生きた、気の遠くなるほどの年数と同じほどの時間が、いまだ自分には待ち受けていることを思い、愕然とする思いだった。
出来ることならすぐにでも、この不浄の魔法の輪から抜け出したいには違いない。しかしスパルタコはまた、それらと同時に、マテオと生きた時間についても思いを巡らせざるをえなかったのである。
100kmごとにエンストする壊れかけた車で、マテオと出かけた旅のことを、スパルタコはたびたび思い出した。ローマから始まってギリシア、トルコまでも、スパルタコはマテオに伴って旅をした。それはマテオの若気のいたり、華々しい新天地を求めるための極貧の旅だったが、毎日の食料にも寝場所にも事欠く始末で、旅の途中には市場に積まれた果実や野菜をこっそり拝借することさえあった。
また、田舎のモスクに潜りこんで眠るうち見つかって、イスラム教徒に追いかけられたこともあった。しかしその道中、透き通ったエメラルド色の海で遊び、見知らぬ異国の街、異国の人をもの珍しく見て回るのは、何とも面白い経験だった。結局どこにも新天地は見つからず、マテオとスパルタコは愚痴を述べながらも再びローマに舞い戻ったのだが、若さゆえのその無謀な無銭旅も、いまとなっては冒険に満ちた愉快な思い出だ。
いや、現在の毎日の生活だってそうだ。画家を目指してはいても、コネも金も家族の援助もなく、いまだにペンキ塗りや大工仕事で生計をたてる自称『人生の旅人』であるマテオの生活は、何とかぎりぎり食い繋ぐ、絶望と希望が入れ違いに訪れるという暮らしだったが、いつも波乱に富んで刺激的だった。喜びも、悲しみも、恐れも、孤独も、スパルタコはマテオと共有していた。ケチで恥知らずなやつだ、と人々に罵られることもあるマテオではあるが、そのふてぶてしい生命力のおかげで、ふたりは今日まで生き延びたのである。
スパルタコ自身、マテオの乱暴な性格に辟易することがあったとしても、血の匂いと孤独と嘆きだけを抱いて生きた十一回の生のうち、マテオとの生活だけが、『愛情』という温度のある感情らしいものを味わうことのできる生活であったことは確かだった。そのことを思うと、自分の魔法を解くために、今マテオの許を去ることは裏切りのようにも思えた。それに自分がいなくなったときのマテオの悲しみようを考えると、スパルタコは身を切られるように辛い。
玄関の扉を開いた途端、激しく飛びかかると、
「わっはっは。今日もなかなか凶暴な出迎えだな。いいぞ、スパルタコ。その調子だ」
嬉しそうにくしゃくしゃに自分を抱きしめるマテオの顔。自分がいなくなってしまったあと、誰がマテオを出迎えるのであろうか。マテオは、本当にひとりぼっちになってしまう。そんなことばかりを考えながら、スパルタコの毎日は鬱々と過ぎていった。
「うん、そうなんだ。スパルタコの具合がやっぱりよくない。残念だけれど、今夜は出かけられないんだ。また今度。うん、ごめんよ。スパルタコがよくなったら、一緒に湖へ行こう。知り合いの別荘があるんだ。いいんだよ、遠慮なんかしなくて。どうせ金満家の別荘なんだから、誰が行ったって構うもんか。迷惑だなんて、僕が絶対にそんなふざけたことは言わせないから心配すんなよ。じゃ、今度。湖の別荘で思い切り楽しもう」
マテオはアフリカの娘にそう電話する。
「おまえのせいだぞ。今夜も彼女に会えないのは」
そうため息をつきながら、スパルタコの頭を撫でた。
その夜は強い風が吹いていた。
マテオのアパートの、建てつけの悪い窓が強い風に煽られてガタガタと鳴り、スパルタコの不安をかきたてた。部屋中に、脱ぎ捨てた洋服や、道で拾ってきた壊れた椅子や、ペンキの缶や刷毛や、使い古された絵の具や、丸められた新聞紙や、ポテトチップの食べ残しや、古い家族の写真、形状をとどめない、何か分からないものらが散らばっている。
逡巡するうち、とうとうスパルタコは満月の晩を迎えた。じっとしたまま床に丸くなり、乱暴な音が鳴り響く窓をそっと見上げる。群青の空には大きな赤い月が浮かび、音もなく昇り始めていた。その月は乾いた風に冴え、いちだんの輝きが、無情で悲しい。
今夜のことを何ひとつ知らないマテオは、日雇いの大工仕事を終え、疲れているのか口数も少なかった。自分の夕食である大蒜と唐辛子とオリーブ油のパスタ、それにツナの缶詰、そしてスパルタコの夕食である、解凍いわしと茹でた白飯を、汚れた皿が山と詰まれた流し台から、あまり汚れていない皿を選んで盛りつける。
「スパルタコ、夕めしだ」
スパルタコは、マテオのその言葉に、ちらと振り向くが、再び力なく窓の外を眺め続ける。
「食べろ。食べなきゃいけない。命令だぞ」
マテオはスパルタコの口に、解凍いわしを運ぼうとするが、スパルタコは口を閉ざしたまま、それを口に入れようとはしなかった。マテオは皿を手に持ったまま。悲しげにスパルタコを覗き込む。
「たのむぞ、スパルタコ」
マテオのその呟きに、スパルタコはクウンと小さく鳴いて、さらに身体を丸める。
月はすでにずいぶん高く昇っている。強い風に運ばれた雲が、みるみるうちに月を覆って月明かりを遮るが、またすぐに月は顔を出し冷たい光を放った。
「満月の晩に、またここで」
あの日、そう言った花売りの顔。瞬かない白濁した片目。萎びた真紅の薔薇の花束。吐き出した煙草の白い煙。
マテオは食事に口をつけないスパルタコの様子に、自分まで元気を無くしたようで、黙々と食事を終えると電気も灯さずテレビのスイッチを点けた。それは友達の中古を譲り受けた、古代的、とも言える代物で、外で強く風が吹くたびに画像が乱れる貴重なテレビだった。マテオは破れたソファに寝転がってぼんやりとそれを観ていた。月あかりの差し込む暗い部屋に、テレビの声が、がやがやと満ちる。
テレビを観ているうちに、マテオは寝息をたてはじめたようだった。スパルタコの寝そべる位置からは、ソファの端にだらりと垂れたマテオの腕が見えるだけだ。
窓の外に浮かぶ月が、誘うように鳴っている。ああ、あれは月の魔の音。
スパルタコはそのときに決心した。やはり行こう。行ってあの魔術師に会う。マテオとも、いずれは別れなければならない定めなのだ。生命あるもののそれが運命。多少遅いか早いかだけの話である。マテオも、いつかは自分なしで生きていかなくてはならない。それにいつか必ず、彼をこころから愛する優しい娘に出会うに違いない。もしかしたら、それはあの、夜のような瞳を持つアフリカの娘かもしれないのだ。
スパルタコはマテオを起こさないように、そっと起き上がると、前足で器用に玄関の扉を開け、音もなく階下へと降りていった。そしてローマの街の迷宮のような暗い路地を、コレ・オッピオの方角へ、強い風に懸命に逆らいながら駆けた。
もう一度人間に戻る。永い、野蛮な魔法から解放される。そしてそうあることが、自分の全うされなかった正当な権利でもある。スパルタコは牙を食いしばって、全力で石畳の路地を駆け抜けた。
夜も更け、固く戸締りをされたカフェの、安普請のトタン屋根がいまにも風に舞いあがりそうに、ガタガタと音をたてて揺れている。夜のとばりに閉ざされた公園は、昼間とはまるで違う顔を持っていた。笑い声も小鳥の声もそこにはなく、色を吸われた緑の木々が、黒い影法師となって大きく揺れている。散在する朽ちかけた遺跡が青い月あかりに照らされた巨大な墓標に見え、まるで墓地にいるようだった。ごうごうと遺跡に反響しながら吹き荒れる風の音は、2000年もそこに漂う亡者たちの嘆く声。
その異様な景色に緊張して佇むうち、強く風に激しく揺れる木々の影が、ひと思いに闇に飲み込もうとでもするかのように、何度も何度も覆いかぶさり、スパルタコはそのたびに鋭い咆哮をあげた。遠くから、その咆哮に応える犬たちの、臆病で神経質な鳴き声が風に紛れて聞こえてくる。開かれたままの重たい鉄格子の扉が、風に吹かれてギシギシと不吉な音をたてた。街灯に照らされ、おぼろに浮かぶコロッセオのその上空、月はもはや手が届かないほど小さく昇っていた。
「やあ、来たな」
何か大きな鳥が、がさがさと巨木の奥でうごめいた。その音に驚いて、スパルタコがはっと振り返ったとき、どこから現れたのか、あの花売りの男はいた。強い風のせいか、片目を激しく瞬かせ、砂漠の人間が着る、踝までたっぷりある長いシャツを纏って、男は立っていた。
「ひどい風だが、おあつらえ向きだ。これぐらいの風なら旅も速い」
呪文のような、祈りのような短い言葉を口のなかで、何回か繰り返すと、男はピュッと鋭い指笛を吹く。やがて、天上から何か軽やかなものが、ふわふわと風に舞い上がりながら近づいた。
「さあ、話はあとでゆっくり。もう時間がないんだ。月があんなに高く昇ってしまった。月がほんの少しでも欠けたなら、魔法の力は半減する。まずは一緒に砂漠へ飛ぼう。次の話はそれからだ。ただ言っとくが、旅の途中、地上のことをほんの少しでも考えてはいけない。地上に執着を持つと、魔法はあとかたもなく消え去るからな。いいか。分かったな。ほんの少しもこころを残すな。何、あっと言う間に砂漠に着くよ。ひと瞬きの我慢」
男はそう言うと、首に巻いていた鮮やかなコバルトブルーのスカーフを解き、強風のなか、器用に丸めてターバンにした。男がそれを頭に巻くと、いつか絵で見た、砂漠の駱駝使いのように見えた。
天上から風に乗って、男とスパルタコの間にふわりと舞い降りてきたのは絨毯だった。年代物らしく、あちらこちらが綻びて、色が褪せている。男はせきたてるようにスパルタコを絨毯の上に乗せ、躊躇する時間さえ与えなかった。砂漠の砂だろうか。前足に、ざらざらとした砂の感触を感じる。
「ぐずぐずしてはいられない。月はいまにも欠けようとしている」
男がもう一度、鋭く指笛を吹くと同時に、絨毯は頼りなげに風に乗った。そして、ゆらりゆらりと、右へ左へと大きく揺れながら、空高くへと舞い上がっていったのだ。それが空へ舞い上がる間、あまりの恐ろしさに、しっかりと爪をたて、スパルタコは絨毯の短い毛並みにしがみついた。牙の根があわずに、身体を覆う毛が逆立つ。男は宙の一点を凝視して、微塵も身体を動かさない。強い風がときおり、ふたりの乗る絨毯をガクンと大きく揺らした。
「ここまで来ればもう揺れまい。そんなにしがみつかなくても大丈夫だ。まあ、ここに来て、おまえの住んだ街でも見納めるがいい」
いままでビクとも動かなかった男は、かなりの高さまで昇ったらしい絨毯の揺れが収まると、よほど嬉しいのか相好を崩し、胡坐を組みなおす。
ローマの街・・・。
スパルタコは男の勧めにしたがって、おそるおそる絨毯の端から、顔を突き出してみる。積み木細工のようなコロッセオが、フォロ・ロマーノが、カンピドリオの丘が、サン・ピエトロ寺院が、テベレ川が、サンタンジェロ城が、無数に輝く家々の灯りのなかに見えた。夜の街を渋滞する車の光粒が天の川のようだ。上空から見たローマは、まるで空を映す鏡だった。地上の星々。スパルタコはあまりの荘厳な眺めに感嘆の唸りを漏らした。
ああ、これが自分の暮らしたローマの街・・・・。
「どうだ、あんな退屈な街でも、ここから眺めると、まるで違う街だろう。そう悪くない街のようにも見える」
男は、まんざらでもなさそうに街を見下ろして、同意を求めるようにスパルタコの背中を撫でた。首筋に、ふいに男の大きな掌の柔らかい温度をスパルタコは感じた。と、そのときだった。スパルタコは反射的にマテオの顔を思い出したのだ。何処だろう。マテオの眠る家は。あのいつも散らかった、窓もドアも半分壊れ、ペンキだらけのアパート。スパルタコは懸命に探したが、絨毯が空高く舞い上がりすぎて、どの辺にそれがあるのか見当がつかなかった。
マテオ・・・・。
スパルタコの胸に強い悲しみが過ぎった。
その瞬間、いままでスパルタコの背中を撫でていた男は、そらぞらしい顔をして、掌をすっと離した。男はもはやローマの街には目もくれず、遥か彼方の空を見つめている。絨毯は街の夜景も見えなくなるほど高く、高く舞い上がった。そこは月も、また、たったひとつの星も見えない闇であった。眼を閉じてもただの闇、開いてもただの闇。風もなく、音もなく、光もない闇。隣にいるはずの男の気配も感じない闇。
どれほどその闇に漂っていただろう。その闇の中、ふいに声が聞こえた。
「スパルタコ」
自分の名を呼ぶ声が聞こえる気がした。スパルタコは辺りを見回したが、見渡す限りの暗黒。きっと空耳なのだ。
「スパルタコ」
魔術師の声?
しかし、この声は。
「スパルタコ、おい、スパルタコ」
マテオの声だ。まさか、こんな闇のなかにマテオがいるはずはない。そう思って、スパルタコがもう一度辺りを見回そうとしたときだ。突然何か、見えない大きな力が、スパルタコの身体をふわりと宙へ持ち上げた。そしてスパルタコをそのまま闇のなか、暗黒の中へと、乱暴に放り投げたのだ。
スパルタコは悲鳴のような鳴き声を上げながら、暗闇のなかをバタバタともがきながら落下した。どこまでもどこまでも落下した。この闇には底がないのだと感じられるほど長い時間、スパルタコは落下し続けた。
「スパルタコ、おい、苦しいのか。何鳴いているんだ」
そこで身体を強く揺すられ、スパルタコははっと眼を開ける。闇は消えていた。鼻先にはマテオの汚れた靴。見慣れた散らかし放題の部屋。
「こんな風の強いところで寝てると風邪をひく」
見上げると、眠たそうな顔をしたマテオが心配そうな顔でスパルタコを覗き込んでいた。魔術師・・・・。
「おい、スパルタコ、こっちに来い。ここで寝ろ」
スパルタコは半開きの玄関のドアの傍らで眠り込んでいたのだ。マテオの指差す方を見ると、ベッドの脇の床には、普段マテオが使っている、毛玉だらけの毛布がスパルタコのために拡げられていた。
窓を見上げると、風は収まり、夜がしらじらと開けていた。紫にたなびく雲が一筋、筆で描いたように浮かんでいる。月は輝きを失って、円形の煙のように薄くなり、すでに魔力を失って空ろだった
結局それが運命だった。
スパルタコは魔法から解き放たれることはなかった。これからも犬なのか、狼なのか分からない獣として、マテオと生きていくことになる。しかし老いた自分には、その生活をいったいいつまで続けることができるのだろうか。また、それが幸福なのか、不幸なのか、スパルタコには皆目分からなかった。そしてこの先待ち受ける八回の狼の生。
マテオの後をのそのそと追いながら、けれど、これが人生というものかもしれない、とスパルタコは漠然と思う。人間としての生を全うできなかったのも自分の運命。そして、これからも獣として生きていかなければならないのも自分の運命なのだ。いや、それはおそらく、すべての生命の人生にもあてはまる過酷な現実でもある。
多かれ少なかれ、すべての生命の人生は、自分の力の及ばない、説明のつかない魔法に支配されているものだ。そしてそれがわれわれ生命の神秘でもあり、どうしようもない悲劇でもあり、喜劇でもあり・・・・・。
Ⅷ
腕の毛にひそむ蚤を取りながら、退屈そうにバラックの話を聴いていた大猿は、蚤をつぶして地面に捨てると、フン、とひとつ手鼻を咬んだ。そしてまだ延々と続きそうなバラックの話に横槍を入れる。
「人間に戻れなかった狼の話はもういいよ。残念なことだった。それにあんたが遠い異国の事情をよく知っていることにも驚いた。実際、あんたはなかなかの物知りだ。しかし、その狼野郎、魔法の途中で地上に執着を残すなんてどうかしているよ、なんだい、たいした男でもない飼い主に心を残すなんて、まったく頼りない狼だ。俺だったら、絶対砂漠まで飛んでみせるのにな」
「まあ、いいさ。狼の話なんてどうでもいい。俺は俺の運命に興味があるんでね。あんたに教えてほしいのは、どうやったらこの魔法が解けるかってことなんだ。いい加減、飽き飽きしたよ、あんたのもったいぶった長い話には。魔法を解いてもらいに砂漠に戻って来たというのに、あんたの話を聞いているうちに、俺はミイラになっちまいそうだよ。猿のミイラなんてみっともなくていけねえよ。で、その片目の魔術師は、もう砂漠へ戻ってきたんだろう。そいつの居場所でも教えてくれるとありがたいんだがなあ」
バラックは口に含んだなつめ椰子の実をぷっと地面の砂の上に吐き出すと、指笛を鳴らす。途端、なつめ椰子の実の種は、蠍に変わり、砂漠の方角へと逃げていった。それを満足そうに見つめたあと、バラックは頭上にかかる見事な満月を眺め、詩人らしく切なげにため息をついた。そして、大猿をなだめるように、こう言ったのだ。
「そう先を急ぐんじゃない。砂漠には使い切れない時間が溢れているのだからね。片目の居場所を知りたければ教えてやろう。しかし、その前に、おまえにもうひとつ魔法の話をしなければいけないと思っている。その話を聞けば、人生がいかに深淵なものなのか、おまえにもきっと分かるようになるはずだ」
そう言うとバラックは、空のコップに、なみなみと椰子酒を注いだ。その甘い酒のせいで、バラックの浅黒い頬には、こころなしか赤味が差している。
思うように話が前に進まずふて腐れた大猿は、アラブの帽子を目深に被って、恨み言を言った。
「おまえなんか、魔法にかかっちまうがいい。一生物語を語り続ける猿になっちまえばいいんだ。あのマラケシュの市場で、ずる賢い猿の子供にこき使われて、物語を語り続ければいい」
その、効力が少しもない大猿の呪詛を嘲笑うように、無尽に続く砂の上、一点の曇りもない砂漠の月が、カラカラと乾いた光を投げかけていた。バラックを睨みつけながら鼻をほじる仏頂面の大猿は、そのぽっかり晴れた丸い月のなかに、黒い影がひとつ、ゆらゆらと横切ったことには気づかなかった。したがって大猿には、その黒い影が絨毯で、その上に乗ったコバルトブルーのターバンの男が、ようやく帰ってきた砂漠を片目で見下ろし、嬉しそうに微笑んでいることなど、知る由もない。
やがてバラックがひとつの物語―それはいったん巻き込まれたら、決して後戻りできない、世にも珍しい砂漠の永遠の魔法の話―を語り始めると、大猿はその話にゆっくりと巻き込まれていった。
大猿とバラックの居るテーブルの上、強い明かりを放つ裸電球の熱に焦がされて、一匹の羽虫が砂の上に落ち、砂混じりの風に吹かれる。
インシャッラー。神のみぞ知る物語。
呪文を唱えるような抑揚のないバラックの声だけが、砂漠の熱い静寂に、いつまでもいつまでも響いていた。
※実在のコレ・オッピオのカフェの女将さんは元気で働き者ですが、親切でやさしい女将さんです。最近では背の高い、なかなかユーモアのあるアフリカ人が女将さんの手伝いをするようになりました。
※イスラムの雰囲気に少し近づいてみたいと、簡単な入れ子式の物語を創ってみましたが、もっと複雑なイスラム世界観を体験したい、という方には稀代の傑作、ロバート・アーウィンの『アラビアン・ナイトメア』をお勧めしたいと思います。
※ローマの花売りのほとんどはバングラデッシュの人々ですが、物語の構成上、ここでは砂漠の魔術師にしました。
▶︎ストーリー展開も作風もまったく異なりますが、狼かもしれない犬を連れたマテオが、主人公のひとりとして、第Ⅰ章の真ん中あたりから登場する、小説「パッショーネ」もぜひ、お読みください!