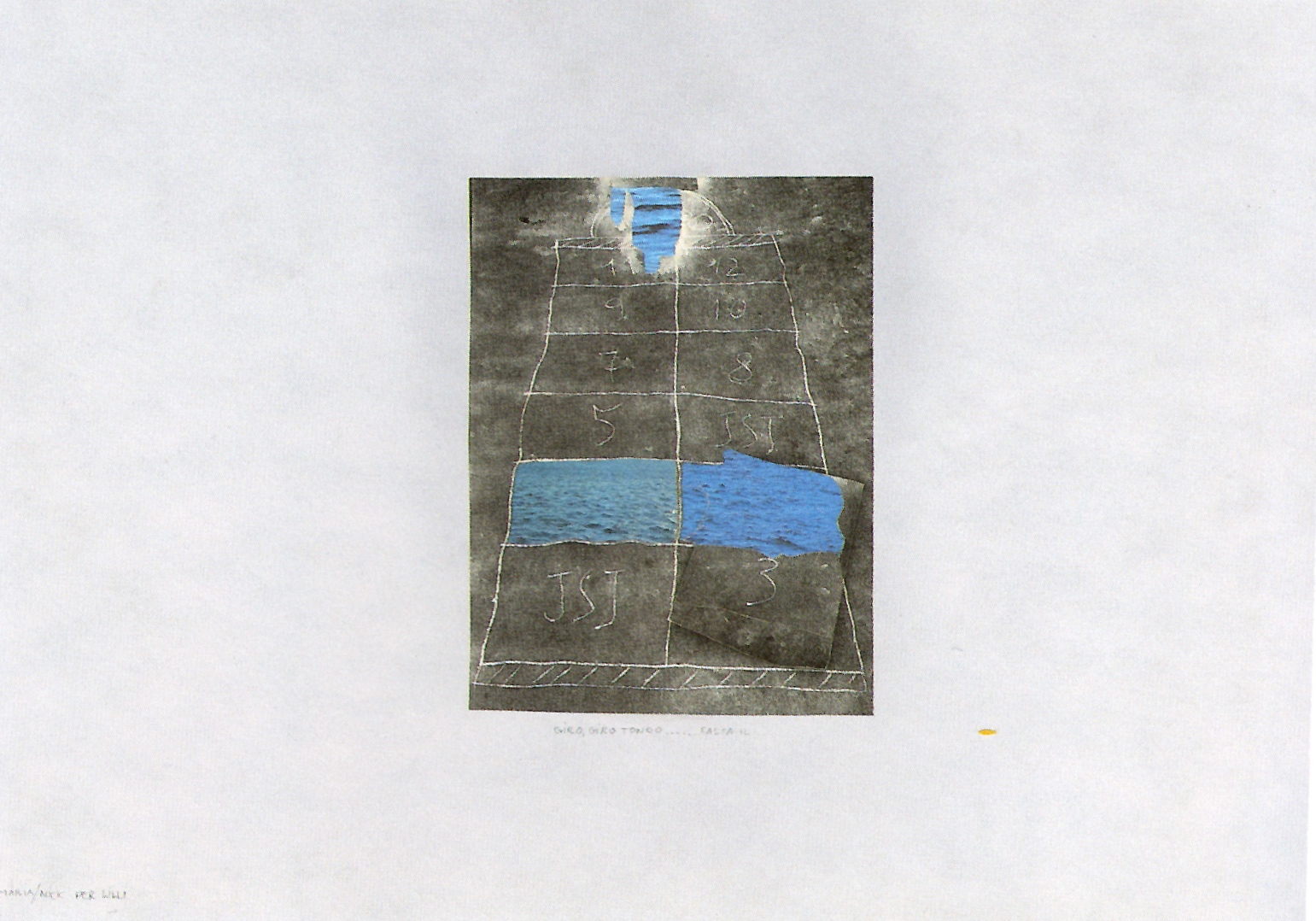詩を書く場合、まず最初に思い浮かぶのが、アイロニーであり、ユーモアだとザイケンは言います。ダヴィンチからパウル・クレー、マン・レイをはじめとする、作家、絵描き、写真家、天使、ギリシャ神話、ローマのモニュメントの数々、墓地から水まで、あらゆるテーマに散りばめられたそのアイロニーを理解するには、しかし歴史を含め、イタリアの文化背景を知っておく必要があるかもしれません。たとえば「ハーメルンの笛吹きとしてのウンベルト・エーコ」という詩があります。
UMBERTO ECO
COME IL PIFFERAIO DI HAMELIN
(ハーメルンの笛吹きとしてのウンベルト・エーコ)ハーメルンの笛吹きはエーコに乗り移った。
文学的伝統の、古く、時代がかった作品にかけめぐる
まったく悪気のない、悩み苦しむ亡霊たちが、
その彼のうしろを追いかける。
ジョイス文学こそ、最高傑作と断言し、
その表現法を真似ようとする者たちを夢の池へ誘いながら。
しかしこの『開かれた作品』の作者は、
幾万のエコー(言葉遊び、Ecoの複数)で、その悪夢を増幅させ、
彼らを溺死させるのだ。
「これはね、ひとつの文化のあり方の要約なんだ。エーコが築き上げた文化を批評してみた。彼が何をしたか、知っているだろう? ジェームス・ジョイスの『ユリシーズ』こそが、最高傑作と断言して、その頃の表現者たちはみな、『そうだ、その通りだ、ジョイスのような表現をしなくてはいけない。ジョイスこそがモデルだ』とばかりに、その方向へ雪崩ていった。エーコは、当時、僕らのメトラ・パンセ(思考のマエストロ)だったからね。ところがエーコときたら、『薔薇の名前』、なんていうゴシック・ロマンとも言える、古いスタイルの小説を書いて、みなを「ええ!まさか!」と驚かせた。そこでエーコ信望者たちは、みんなどうしていいか分からなくなって、道に迷ってしまったんだ。弄ばれたんだね。この詩は、そして僕の文化に対する考えを要約したものでもある」
「フェノーメノ(現象)をフェノーメノとして観察する。つまり『現象学』的文化観察が、詩という形式で批評させた、といえるかな。イタリア文学の仲間たちは、あの小説の発表当時、ひどくウオサオしてね。彼らは多分、ちょっとした格安ホテル、あるいはペンションを見つけた、と思っていただろうに気の毒なことだった。エーコは知っての通り、Semiologo、記号学者で、ロラン・バルトの研究など、学者としては素晴らしい科学者、そしてマエストロだ。でも、文学者、とは言えないかもしれないね。学者と文学者は違うものだから。いずれにしてもエーコはベストセラーをたくさん出してるし、100万のエーコ(エコー:反響)で世の中を満たしたことは事実だけれど」世の中に満ちる、その「100万のエーコ」を想像すると恐ろしい、とザイケンとともに笑いましたが、ということはザイケンの詩を読むには、ある程度知識が必要ではないか、と本人に問うてみました。
「そうなのかな。確かに知識を必要とするものもあるかもしれないけれどね。しかし『詩』は本来、文化などを感じさせてはいけないんだ。僕はintellettualità ー知性、というものは、とてつもなくくだらないものだと思っている。知性が何より馬鹿馬鹿しいものだとね。すべてのあらゆることを理詰めで捉えること、合理的にメカニックに構築する、という表現は、編集しなおして、再創造していくことが可能だからね。この再創造、再構築は確かに頭のいいやりかたかもしれないが、でも、ordine, riordine della naturaー本来の形を秩序をもって、構築、再構築、再配列する、というやりかたは、非常にくだらないものでしかないね。表現としては、まったくつまらない」
「たとえばユートピア思想。戦後、僕の仲間の間では、ユートピア的な世界のあり方が、非常に知的に議論され、そして結局成功しなかった。ならばユートピアについて長い時間をかけて議論するなんて、まったく無意味なことじゃないかい? 僕は、政治なんてどうでもいいんだ。ちっとも面白いとは思わない。僕の友人、文学の同僚たちのなかには、政治的な活動に走った者たちも大勢いるんだけれどね。僕らの時代、政治的な流れに身を投じることで生きる糧を得る、ということもあったからね。ある政治的流れに従っていれば、仕事も入ってくる、書く機会を与えられる。政治的背景が個人の野心を満足させる、というシステムがあった。それと同時に、彼らは、新しい社会、新しい世界を作っている、という満足感も味わえた。この満足感は2世代の脳裏に焼きついたが、結局何の変化も起こさなかったね。ユートピアなんてどうでもいい。それが重要だなんてまったく思わないよ。僕は個人主義、それも完璧な個人主義者だからね。個人主義者として、社会の集団的解決にはまったく興味ないんだ」
しかし芸術家というのは、多かれ少なかれ、個人主義の傾向があるのではありませんか?
「いや、あらゆる分野で、政治的、あるいは文化的な流れを見極めて、集団的な表現、つまり誰にでも有益な表現を目指す者だっているじゃないか。そんな能力がないにも関わらず、みんなに気に入られようとして。結局そんな者たちはただの『無能力』なんじゃないかい?」
「そういうわけで、僕は政治的なことにはまったく興味はないんだが、『地政学』には大変な興味がある。それをひとつの、素晴らしい芸術だとも思っている。それぞれの国の戦略は、過去の長い時間の歴史から構築されているし、それぞれの国の野心を物語っている。戦うにしてもいろいろな理由があるだろう。経済、産業、イデオロギー、民族の威信。僕は常に『地政学』には大きな注意を払っているんだ。詩のテーマにもなる。僕の詩には、マレーシア、日本、中国を題材にしたものが多くある。イタリアには、しかし残念ながら、『地政学』に熟知する者たちが少ないね。僕たちは世界のリアリティというものが、どのように動いているか、直視しておくべきだよ。過去の歴史を含むグローバル・リアリティがわからなければ、未来が見えない。僕は自ら『地政学』を体感しようと、過去、あらゆる場所に旅をした。中国、米国、フランス、ドイツ、ロシア。ドイツ語、フランス語、英語、といくつかの言語も勉強したしね」
YAMAMOTO
いかにして哲学を応用するか
その方法論の訓練中
未来、連合艦隊司令長官となる男は、
風を舵に、小川に着水した一枚の紙切れの
行き先を瞬時に悟る。
メタルブルーの大蝿が一匹、
流れにまかせて、呑気に運ばれている。
虫は飛び立ち、自らとそっくりの大蝿たちと交差、
決闘の真似事のあと
再び乗船しようと高度を下げる。
連合艦隊司令長官は
それだけで核心を理解した。
その飛行術が
日本海軍に伝授されたのだ。
(ザイケンは日本文化、精神性に深い興味を抱き、山本五十六を題材に、自身のイメージする自然と直結した「禅」的世界を書いている)
「僕の詩は、街をぶらぶら歩いているときに、突然生まれる。アイデアが訪れるときは、一瞬だよ。点滅みたいなもの。僕はOccasionale(偶然、たまたま)な詩人でね。ある意味、古典的な詩人ともいえる。昔の詩人というのは、街をぶらぶら歩いているとき、偶然会ったご婦人から『わたしに詩を書いてくださる?』と注文されると、その場で即興で書いたんだ。僕も注文を受けて詩を書くこともあるんだよ。たとえば何かの祝い事があるとき、夫から妻へ、あるいは恋人へ送る詩を書いてくれ、と頼まれると引き受けるんだ。詩を『売る』ってことだ。生きていかなくちゃいけないからね。稼がないといけない。そしてそれを非常に気高いことだとも考えている。いまのところ、イタリアで注文に応じて詩が書ける詩人は、僕をおいて他にはいないと思うね。おかげで僕はいまだに生きながらえているのさ」
「僕の詩は、したがって世界を観察して生まれてくるのであって、感情、心情から生まれてくるのではない。内側から生まれるのではなく、外界というひとつの枠から生まれてくるんだ。ロマンチシズムはこころからのみ生まれるわけじゃないだろう? 外界に生まれたロマンチシズムに誘発され、センチメント(感情)が生まれる。わたしはとても俗っぽい詩人でね。友人たちと遊ぶのは楽しいし、どこかのフェスタに出かけるのもワクワクする。昼食会に呼ばれるのも面白い。人々を眺めて、人々を観察して、その会話から『詩』が生まれることもあるしね」
「平行して、『演劇』がある。昔、演劇を学んだという経緯もあって、脚本、ラジオドラマを書いてきた。それを書いているときに『演劇』というものを理解できたとも思う。演劇は僕の詩と非常に近い場所に存在していて、それは平行してあるものだからね。演劇は、ひとつの見える世界を形成しているが、僕の書く詩も言葉がつくる、目に浮かぶであろう世界を表現している。僕の詩はすべてワンシーン、そのなかにひとつのストーリーを形成している」
「詩で最も大切だと思っているのは『経済性』だね。つまり、エッセンシャルでなければならない、ということ。センチメント、アイデアともに本質までたどりつかなければならない。たとえば、非常に知的に書かれ、飾られた詩というのは、実は『エラー』かもしれないね。ひとつの詩のなかに、多くのコンセプトを入れ込む詩人がいて、その詩人は、ある意味、文化的教養の高い詩人でもある。しかしアイデア、コンセプトというものは、本当はたったひとつあればいいんだ。だから僕は俳句やアフォリズムが好きなんだよ。詩にアイデア、コンセプトがシンプルに現れるからね。知性だの、頭の良さ、だのというものは『詩』を破壊する。知性がひけらかされた詩はだめだな。知的なコンセプトが盛り込まれた詩は、廃墟のようなものだよ。詩人はバカなほうがいいんだ」
HAIKU (5,7,5 sillabe)
Passando le nuvole
si copre
la luna di miele.
雲ゆきて 蜜月を隠す
Si distaccano dal corpo
i volatili pensieri
a lui resta attaccata la pigra amina.
ちぢに飛ぶ思考をさえぎれば、彼に残るは怠惰な魂。
Autunno
arrossiscono le foglie
pudore della vecchiaia.
秋 老い恥じらって 赤くなる葉っぱ
Ardono le travi incrociate
il fuoco
gioca Shanghai.
十字の木の梁 燃えさかり炎、上海を遊ぶ(訳不能)
All’amo affiora
la razza
aquilone d’acqua.
釣り針に姿現すエイ 水の大鷲
AFORISMI
Il cielo non legge, e neanche
parla le lingue umane,
le ascolta ma non le capisce.
天は読まず、人間の言葉を話さない。
それを聞くが、まったく理解しない。
I teologi sarebbero
i diplomatici
della religione?
神学者というのは、宗教外交官なのかい?
Mi cadono i capelli
e anche i pettini
perdono i denti.
髪は抜けるし、櫛の歯も抜ける。
「僕はインスピレーション、霊感というものを信じている。義務で書く、ということもあるけれど、しかしやはりそれも『霊感』に導かれてのことだね。たとえば頼まれて、ひとりの人間の肖像を書くとしよう。わたしは机に向かってそれを書く、ということはしないんだ。インスピレーションから導かれるまではね。『霊感』があれば、たやすく詩が書ける。すべては無意識、与えられた天分から現れるんだが、インスピレーションを与えられた、ということは幸運なことだね。それがない人間は、どんなに大変な苦労をするか、と思うよ」
「僕はとても怠け者なんだ。本当のことを言えば『何もしたくない』というのが本音。僕を詩作に駆り立てるのは、『絶望』であるとしか言いようがないね。空腹、不幸、社会への恐怖、これらが僕に詩を書かせるようになった。そうじゃなければ、何も書かなかったし、何もしなかっただろう。人生を楽しんで、それで終わりだったはずさ。社会、つまり世界というものは、いつも何かを要求してくるだろう? 世界というものは、例えば、工場で働く工員でなければならない、とか、オフィスで働かなくてはならないとか、なんらかの役割を担う義務を、遠慮なく、ずけずけと要求してくるものだ。それは脅迫にも似たものだよ。何をするか探しなさい。何らかのアイデアを持ちなさい、とね。それは『絶望』的なんだ。だから僕は常に絶望している。何をしていいのか、さっぱり分からないからね」
しかし逆に、「希望」というものも、一種の幻想というか、「罠」でもあるのでは?
「さあ。僕は希望というものを一度も持ったことがないから分からないんだよ(笑)。たとえば、どうしても書かなくてはならなくなって、本を書くとするだろう? しかしその本が売れればいい、なんて希望を、一度も持ったことがないんだ。なぜなら書き終わったときに、その本が売れるであろうことを、もうすでに知っているからなんだ。本の編集が終わった時点で、本が自ら読者にふさわしい人を見つけることは、もう分かっている。それでも僕は常に『絶望』していてね。だって僕は書きたくないんだ(笑)。書くことなんてどうでもいい。あちこちを出歩いて、綺麗なご婦人がたを眺めて、友人たちと楽しんで、酔っ払って過ごしたい。それこそが人生じゃないか」
「しかしね、僕はシャワーも浴びなければならない。夕飯の買い物にも出かけなければならないし、料理もしなくてはならない。それすべてを全部自分でしなければならない。このバラックだって、何かが壊れれば、自分で修理しなくちゃいけない。屋根も、床も自分で張ったんだよ。壁の修理だって自分でする。お手伝いさんを雇う余裕はないからね。しかも僕には、すべてをやり遂げるキャパシティがあるんだ。でも、もし僕本来の本質を鑑みるなら、本当は何もしたくない。ベッドに寝転がっているのも好きだ。毎日毎日寝転がって暮らしたい。それが願いでもあるかな。僕はオブロモビアーノなんだよ(オブロモボは、ロシア文学、Ivan Aleksandrovič Gončarovの書いた小説の主人公。何もせずに寝転がって過ごす人物)」
「怠け者だからこそ、絶望するんだ。何もしたくないのに、どうしてもやらなければならないことができて、その事実が僕を絶望させる。誰かに詩を書いてほしい、と頼まれるとするだろう? そのリクエストを受けたときは、とても幸せな気分になるが、その気分もあっという間に消えてしまう。書かなければならない。義務。分かるかい? これがチャールズ皇太子の言う、遵守しなければならない義務を負わせて、市民を被支配者にする、規範、常識、モラルなんだ。マルコ・アウレリオ(マルクス・アウレリウス)も、書くことは自分にとって義務だった、と言っている。天才的な皇帝だってそう言うんだから。すべてが義務なんだよ。『あの川を渡らなければならない』、止まることは許されないんだ」
ところで、ローマという街についてどう思っていますか?
「ローマの歴史的なポジションはヒューマニスティック、ということだね。そのおかげで国際的な都市にもなれた。ローマにはさまざまな言語が飛び交い、パンテオンはあらゆる宗教を持つ古代ローマ人すべての祭壇でもあった。ローマという都市は何もかもを受け入れる都市なんだ。何より、ローマが守った市民の『権利』ーつまりローマ法が何より大切な基本だと思うね。自分の権利を主張するために、異邦人であろうと、他宗教の民族であろうと、市民でありさえずれば裁判を起こす権利を有していたんだから。ローマ法がなければ、専制的になり、市民に自由もなかっただろうね。この法のおかげでローマ帝国は8世紀もの間、永らえることができた。すべての自由が保障され、もちろん奴隷もいたが、その奴隷もやがてローマ市民として認められることもあったわけだしね。その奴隷がのちに大金持ち、権力者になることもありえた」
「古代ローマのあり方は、ひとつの社会モデルとして、アメリカも英国もずいぶん研究しているし、いまだにみんなが大好きでもあるだろう? なぜならローマの世界観は、自由な世界観、多様性の世界観だからだ。つまりローマという都市は偉大なイデアなんだよ。死ぬことのない、永遠のイデア。『あなたはどこの国の人間で、どの民族に属しているのか』などと区別されることなく、ローマ市民でいられるなんて素晴らしいことだ」
「実際僕は幸運だったよ。外国で生まれたが、この街で暮らすことができたんだからね。ローマは僕にあらゆることを考える機会を与えてくれる。美術館、教会、寺院、彫刻、なにもかもが魅力的だ。ローマ市民である、ということ。それが僕の人生における基本だね。本質的に言えば、ローマ人たちは『民主主義』ーそれは完璧ではなかったがーを実現しようと試みたんだと思うよ。たとえば『水』を市民に平等に与えたよね。水は人間にとって、必要欠くべからざるもので、何より『民主的』であるべきものだからね。それにローマには文化があった。哲学者、詩人。もちろんギリシャのそれらに比べると多少劣るが、いずれにしても偉大な文化が存在した。水道をはじめとするインフラ、そして建築、モニュメント、彫刻、そしてなにより道路の整備をしたことは偉大だよ」
神(あるいは神々)を信じているか、との問いには、「利便性を考えると、時と場合によってはね、と答えておこう。神に対する憤怒、という意味では、わたしは無神論だけれどね。でも、時と場合によっては、話し合いにも応じるよ。もしDivinità(神、神性。キリスト教ではない神)が、もし僕に、絶対に死ぬことがない、と約束してくれるなら、いつでも回心する用意はできている。詩のなかで、いくつかそんなことを表現したことがあるよ。次は印刷機を変えよう。こんなに早く人生が終わってしまうなんて。次の人生では他の印刷工房に行かなくては、とね」
「自然というものは、循環する機械のようなものだ。Paradivina(ほとんど神のような存在)。 深遠な神秘ともいえるべきもので、そこに存在する繊細さ、「感受性」は言語を絶するものだ。われわれすべても、その深遠なる神秘に抱合されるミステリーだよ。神たちのエンジニアとしての素晴らしさは例えようもない。自然の優れ様は、常軌を逸している。僕たちがナノテクノロジーと呼ぶ、自然のミクロの世界の凄さに驚くだろう? バクテリアの世界とかね。その世界は『死』をも含んでいるわけだが、自然は循環し、リプロデュースし続けるメカニズムを持っている。それも次第にイノベーションしていくメカニズムも併せ持ちながら、世代を循環させていく」
「と同時に自然はカオスでもあるからね。あまりにたくさんの種を発明しすぎて、まるで神たちそのものが混乱しているかのようだよ。生物の種が多すぎて、バクテリアまで含めると、あまりに複雑すぎて、『こんなことが可能なのか?』と目がくらむようだ。神(あるいは神々)は多分頭が良すぎて、世界を混乱させることにも長けている。その混乱を引き起こす者である『神』が、素晴らしい自然を生み出しているんだが、宇宙の星々に関してもそうだ。宇宙科学者たちは『そのメカニズムに奇跡を感じる』と口を揃えて言うが、宇宙は確かに僕らを驚愕させる」
「自然というのは、ひとつの大きな流れ、戦争だ。闘いの連続だ。爆発、ブラックホール、星の衝突、考えられないカオス。しかもそのカオスは常に連続している。宇宙、そして世界は信じられないほどヴァイタリティに満ちたエネルギーで出来上がっていて、それがずっと続いているんだ。ファンタスティックだと思わないかい? 自然には秩序がまったくないように見えて、実は秩序がある。やっと秩序を見つけたと思えば、今度はそれを見失う。そう、そういうわけで、わたしは神、神性に関しては、いつも曖昧なんだ」
「神(あるいは神々)をリスペクトしたいとは思うよ。ギリシャ人は、自然の動きとそのパワフルなエネルギーを認識していて、それを宗教に置き換えていった。ギリシャの神は自然崇拝から生まれたものだ。そしてUlisse、ユリシーズがその論理をひっくり返すのが面白いね。神々の秩序から逃れる人間が現れたということだからね。古代、決闘をするとき、互いに自分の名前、どの家系からやってきたか、をまず最初に名乗っていた。ところがユリシーズはひとつ目のチクロペに『自分は何者でもない』と言うんだよ。自分自身という存在から遠ざかるとき、自分自身は『何者でもない者』になる。これはテクニック、自分自身を隠すテクニックなんだ。そしてその場合、言葉というものがテクニックなのかもしれない。『おまえは誰だ』『何者でもない』チクロペは『わたしは盲目になってしまった。誰がこんなことをしたんだ』と嘆くが、ユリシーズは『誰でもない』と答える。みなが笑うんだよ。『誰でもない』『誰でもない』これでは誰をも攻撃できない。誰でもない、目に見えない者を触ることも、捉えることもできないからね」
「いいかい。Invisivilità 、『不可視』であることは、言葉を駆使したテクニックなんだ。これは覚えておくべきだよ」
*2023年追記 ローマの人々に愛されたヴァレンティーノ・ザイケンは、2016年に突然亡くなることになりました。その後すぐ、かつて詩人が住んでいたバラックを訪ねると、庭に咲き乱れたジャスミンの香りが門の外まで溢れて、あたりに柔らかい空気が流れていたことを思い出します。それから5年ほど経って再び訪ねてみると、もはやザイケンのバラックは影も形もなくなっていました。