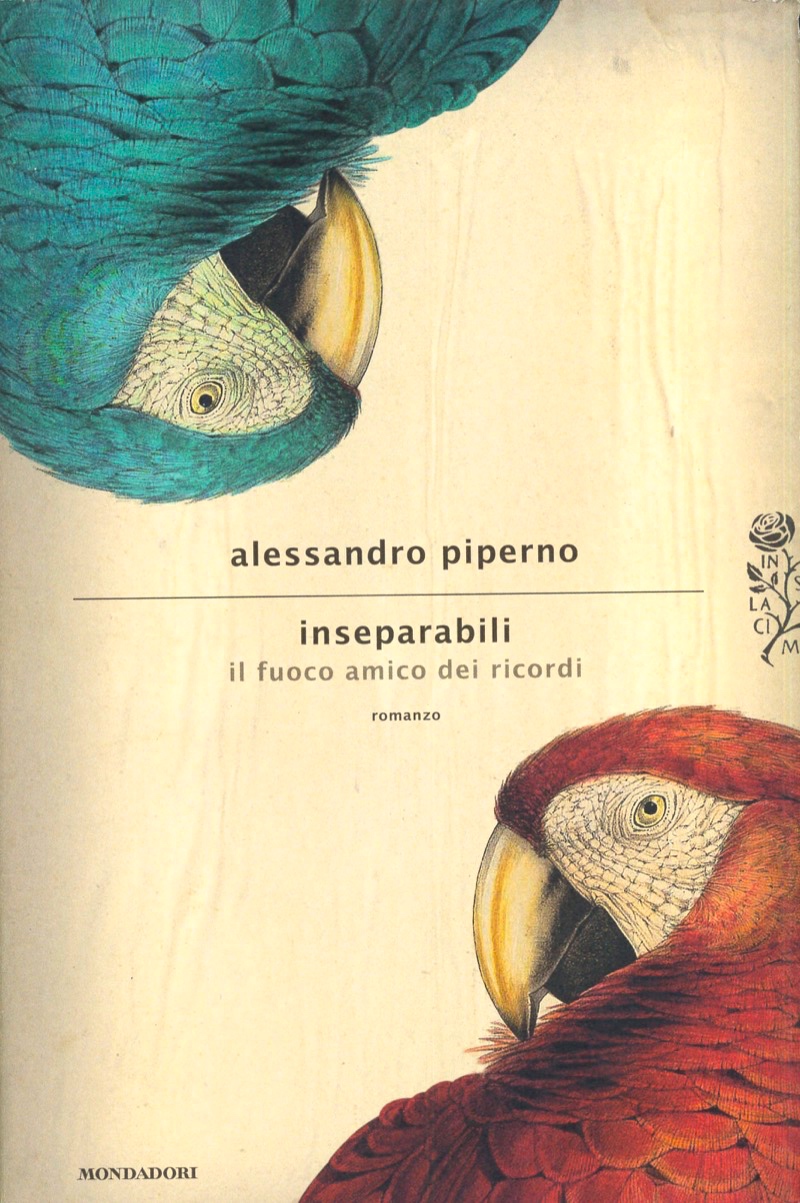その若さにも関わらず、イタリア現代文学、そして映画について、これほど繊細なアンテナ、審美眼を持ち合わせる人物をわたしは他に知りません。二宮大輔氏、第1回目の寄稿(写真はアレッサンドロ・ピペルノ“con le peggiori intenzioni“表紙より)です。
イタリア長期留学のために初めて足を踏み入れた地は、シチリア島北東に位置するタオルミーナだった。
小さな町にも関わらず、そこには目に見えない小宇宙が広がっているような気がして、私はこの国をいつまでたっても掴みきれないでいた。その感覚は今でもさして変わりない。それでもイタリア語の小説を読もうとしたきっかけは、漫然とそこにいるだけではちっとも到達できない小宇宙の深層に、小説を読むことで道が開けるように思えたからだ。事実、その勘は当たっていた。
タオルミーナに唯一あった書店のお姉さんにお薦めの小説を尋ねたところ、返ってきた答えはピエル・パオロ・パゾリーニの『生命ある若者』(Ragazzi di vita)。1950年代のローマ郊外の荒んだ貧民街の若者たちを活写した作品だ。その内容の細部まで理解できたのはずっと後になってからだが、小宇宙を知るきっかけにはもってこいの小説だった。かくして留学元年、私は自分にとってのイタリア文学の役割を認識しはじめた。
以来、学校で、本屋で、図書館で、招かれたホームパーティーで、実に多くのイタリア人と小説を話題にしてきた。それにも関わらず、アレッサンドロ・ピペルノを紹介してくれたのは誰だったか思い出せない。タオルミーナの書店のお姉さんのことは覚えているのに、彼のように重要な作家に出会わせてくれた恩人のことを忘れているのだから腑甲斐ないかぎりだ。
とにかく私がピペルノを知ったのは、彼の処女小説”Con le peggiori intenzioni”(未邦訳『最高の悪意を持って』)が発表された2005年ごろだった。第二次大戦後からアメリカ同時多発テロが起こった2000年代初頭まで、ローマに住むユダヤ人ブルジョア一族の退廃ぶりが、一族の末裔ダニエルの皮肉たっぷりの視点で描かれた作品だ。現代イタリアにおけるユダヤという主題が注目を集め、20万部を超えるベストセラーとなった。だがその内容は、ユダヤの血筋が入ったピペルノ自身をも自嘲するものでもあり、格式高い文体と相まって、耽美過ぎるという否定的な批評も被った。
また、三十代半ばにしてすでに大学でフランス文学の教鞭をとっていたピペルノは、とにかく博識で、さまざまな分野に精通している。アメリカ人作家を招いての公開インタビューを見に行ったことがあるのだが、インタビュアーのピペルノが喋りすぎ、「本人にもっと喋らせろ」と観客からヤジが飛ぶほどだった。優秀なのに人から反感を買うのは、良くも悪くも人気作家の宿命かもしれない。いっぽう私はというと、理由もわからぬまま、ますますピペルノにのめり込んでいった。当時アルバイトをしていたローマの日本食店に客として訪れた彼と短い会話を交わせた個人的体験も、それに拍車をかけた。
そして2012年、三作目の小説となる”Inseparabili”(未邦訳『ラブバード』)が国内最大の文学賞ストレーガ賞を獲得した時点で、私のピペルノ熱は最高潮に達する。これは2010年に出た二作目”Persecuzione”(未邦訳『迫害』)の続編にあたる長編小説だ。この二部作には”il fuoco amico dei ricordi”(思い出の友軍誤爆)という意味深長な副題もついている。何が思い出で何が誤爆なのか。まずは”Persecuzione”から順に見て行きたい。
1986年、高名な医師であるユダヤ系イタリア人レオ・ポンテコルヴォは、妻と思春期に差し掛かる二人の息子たちとともに豪邸に住んでいる。申し分のない生活を送っていた彼だが、テレビニュースで突然、息子のガールフレンドを虐待していたと報じられる。寝耳に水の醜聞で一気に人生を転落したレオは、家族とも会うことを拒み、家の地下室に逃げ込む。隔離されて暮らすうちに、疑念と困惑が膨らみ、レオは徐々に精神を消耗していく。
続いて”Inseparabili”だが、こちらは二人の息子フィリッポとサミュエルが主人公だ。2011年、自分の幼少期の経験を物語にして突如として大成功を収める漫画家のフィリッポ、投資家となったが事業に失敗するサミュエル。それぞれが15年前に父が起こした事件の思い出を胸に抱え込み、辛い現実に立ち向かう。互いに疎んじ、隔たりがあるように見える兄弟二人だが、一匹だけでは生きることのできないオウムの一種ラブバードのように、結局は離れることができないと身をもって理解する。
ピペルノが描く主人公たちはいつも破滅に向かう。それも、粉砕骨折するように、心にひどい傷を負いながら。このピペルノの同族に対する手厳しい眼差しはどうだろう。ユダヤ人であることを前面に押し出しつつ、ユダヤを否定するような作品をつくる彼は、インタビューで自分のことを「ユダヤのペテン師」だと言い切る。完全なイタリア人ではないが、かといって完全なユダヤ人でもない彼だからこそ書けるローマのユダヤ人の堕ちっぷりからは、イタリアの小説がこぞって表現したがる「現代イタリアの退廃」よりも、さらにねじ曲がった愛憎を感じる。そのねじれ具合がイタリアで暮らす外国人であった私の波長により合っていたのだと今では思う。
*ちなみにストレーガ賞獲得に興奮した私はピペルノに向けて手紙を書いた。当時ピペルノは教授として大学に籍は置いていたが、すでに授業を受け持っていなかったので、ローマ郊外にあるトル・ベルガータまで行き、教職員のレーターケースに手紙を投函してきた。内容は「オメデトウゴザイマス。つきましてはぜひあなたの作品を日本語に翻訳したいです云々」。なんともはた迷惑な読者だ。当然のことながら返事はもらっていない。嫌われ者のペテン師が、わざわざイタリア語もろくに喋れない日本人を親切に相手してくれるはずもないだろう。だが、彼の小説が日本語に訳されて、その特異な視点を通してイタリアという小宇宙を知るのも悪くないように思う。