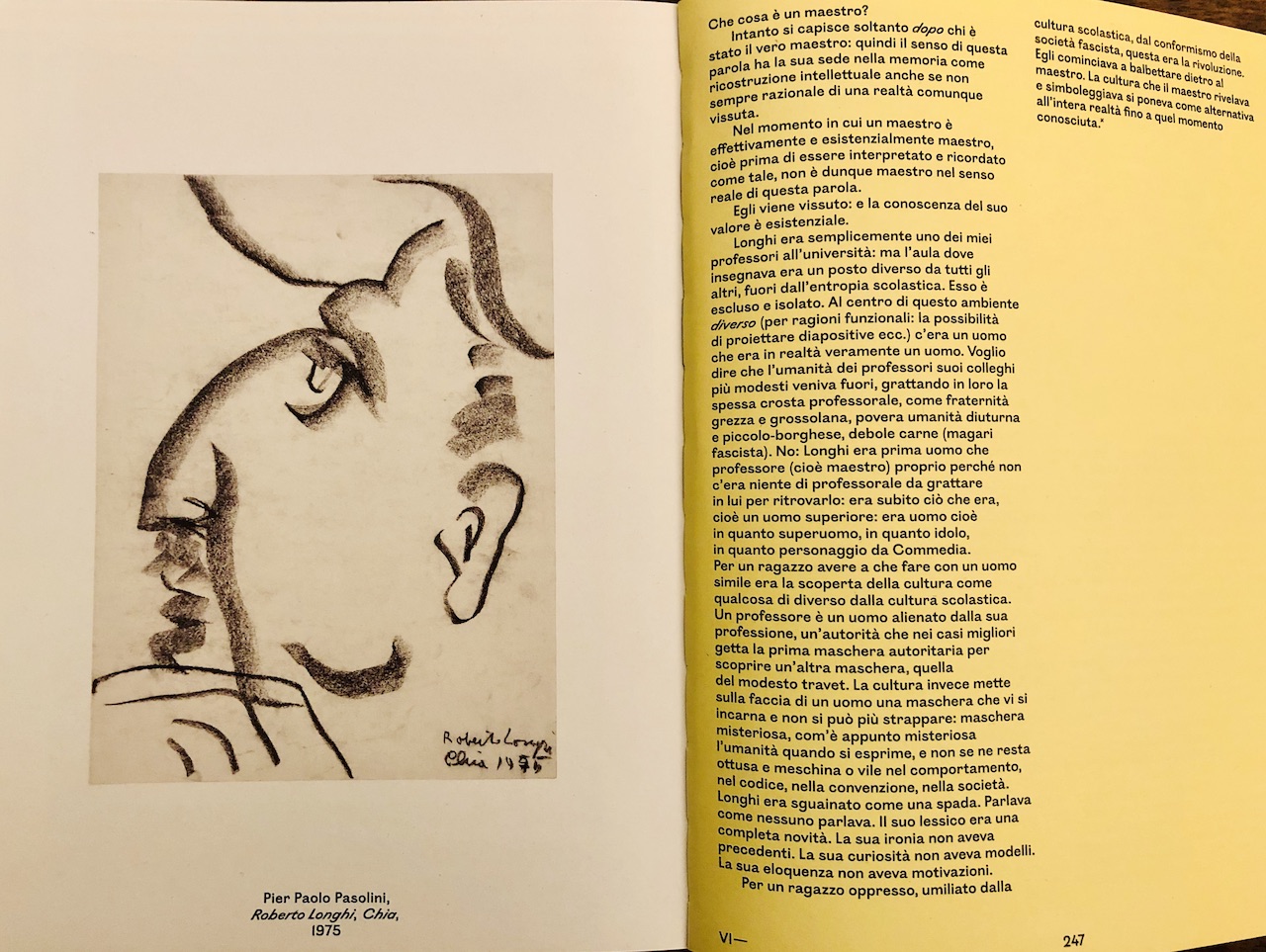19世紀、ようやくその『天才』が認識されたカラヴァッジョとカラヴァッジョ派
今でこそカラヴァッジョと言うと、天才の名を欲しいままにする『偉大な画家』として、世界中から熱狂的な称賛を集めていますし、もはや何ひとつ、カラヴァッジョについては語ることができないほどに研究され、評論し尽くされています。そして近年、アルテミジアの人気も同様にうなぎ上りとなっている。
しかし実のところは、つい70年ほど前まで、カラヴァッジョも、カラヴァッジョから連なるカラヴァッジョ派(アルテミジアを含め)も、忘却の彼方、記憶の深い闇に、すっかり置き去りにされた画家たちでした。
350年もの間、カラヴァッジョはミケランジェロやラファエッロと肩を並べる天才として認識されることはなく、アルテミジアに至っては、数々の作品が父親のオラツィオの手による、と考えられたり、オラツィオの弟子の作とされたり、作品があちらこちらに散らばり、最近になってようやく本格的な研究と鑑定が進められるようになりました。
では、なぜカラヴァッジョとカラヴァッジョ派が、これほど重要視されるようになったのか。そのきっかけを作ったのが、ボローニャ大学の教授であり、美術評論家のロベルト・ロンギなのです。
カラヴァッジョが当時の画壇にどれほど衝撃を与え、イタリア(バルトロメオ・マンフレディ、マリオ・ミンニーティなど)だけではなく、スペイン(ディエゴ・ベラスケスなど)、フランス(シモーヌ・ブエなど)の多くの画家たちに大きな影響を与えたかを、ロンギが研究し、世界に再提案しなければ、カラヴァッジョもアルテミジアも現代に甦ることはなかったと言えます。
そしてそれは、まるでロンギが唱えた呪文で死者たちが甦ったような、一種魔法的な出来事でもありました。
1951年、及び1953年に、ロンギがオーガナイズしてミラノで開かれた展覧会が、カラヴァッジョ再生の扉となりました。それらの強烈な絵画の数々に突然対峙した世界は、魂を揺さぶられ騒然とし、1610年にのたれ死にしたまま行方不明だったカラヴァッジョの存在を、ようやく思い出すことになった。さらには誰もが「カラヴァッジョが存在しなければ、近代絵画の発展はなかった」とまで口を揃えるようになりました。

1951年、ミラノのPalazzo Realeで開催されたカラヴァッジョとカラヴァッジョ派の展覧会。3ヶ月で40万人の観客を集める『信じがたい大成功』を収めたそうです。artslife.comから転載。
考えてみれば、鑑賞者の審美眼などはあまり当てにならないものです。カラヴァッジョが亡くなって350年が過ぎて、時代がようやくカラヴァッジョの感性を理解する深みに達したのか、皆が「素晴らしい!」というので素晴らしく見えるのか、芸術に対する感性は、時代や空間で大きく変わります。19世紀までは、ラファエッロ、グイド・レーニという繊細で優美、どこか貴族的な画家たちがイタリアの伝統絵画のシンボルでもあったのです。
また、アルテミジアを巡る研究を進めたのは、ロンギの妻であり、数々のすぐれた美術評論を残したアンナ・バンティでした。アルテミジアを描いたバンティの小説の初稿は戦災で失われたそうですが、そののち(1947)にまとめられた本は、書店にアルテミジアに関する本を探しに行くと、今でもまず最初に薦められます。
現代の研究によると、カラヴァッジョは1500年代の終わり、ローマに彗星のように現れた天才画家として高い評価を受け、熱狂的な支持を集めると同時に、娼婦やテベレ川で上がった水死人を聖母のモデルにしたり、ジプシーを題材にした絵画を構成するなど、高位聖職者やエレガントな保守派貴族には眉をひそめられることも多かったと言います。
傲慢で鼻持ちならない、なかなかの問題児だったその彼は、しかし下書きもせず、モデルを一眼見て一気にテーマを描き切る、アクロバティックな画家でもあった。
悪所通いで身を持ち崩し、娼婦に入れあげ、剣を振り回す暴力的な喧嘩や揉め事も絶えず、遂には殺人を犯して、カラヴァッジョはローマを追放されます。その後は教会の恩赦を受けてローマに戻ることを夢見ながら、友人たちの援助を受けつつ、マルタ、ナポリ、シチリアを転々とし、最終的には39歳で病気で亡くなっています。
こんな犯罪人としての暗い人生のせいで、歴史はいったんその画家を暗闇に葬り去り、トスカーナの教会の共同墓地でその遺骨が見つかったのは、なんと2010年のことです。
さて、政治家としてはどうも信用できないのですが、美術評論家としては、分かりやすく物語性のある分析に定評のあるヴィットリオ・スガルビィのカラヴァッジョの評論は、とても興味深いものでした。
その際スガルビィが、ピエール・パオロ・パソリーニとカラヴァッジョの審美的共通点を指摘して、ハッともした。というのもわたし自身、両者の着眼点、そして人生の有り様が非常に似ていると感じており、かつて両者の共通項を調べた際にロベルト・ロンギの名を見出して驚いたことがあったからです。
パソリーニ、そしてベルナルドとジュゼッペの父親である詩人アッティリオ・ベルトルッチは、ともにボローニャ大学でロベルト・ロンギの講義を受けています。したがって、現代のイタリアにいまだに影響し続けるパソリーニ、そしてベルトルッチ兄弟の美意識の核に、ロンギが強く影響していることに疑いの余地はないでしょう。つまりカラヴァッジョの感性は、ロンギという人物を通して、絵画だけではなく、1900年代の文学、映画の世界にまで大きな影響を与えたということです。
スガルビィは、バロックにはふたつの方向性があったと言います。ベルニーニやボロミーニのように、教会という最高権力にバックアップされ、セレブリティとして豊かに、潤沢に美を表現したアーティストと、カラヴァッジョのように、底辺で懸命に生き抜く、イタリアでGli ultimi(ウルティミー最貧困層)と呼ばれる人々の生命力を、野生の美として、ドラマティックに昇華させたアーティストが存在したというのです。
そして、そのカラヴァッジョの美意識が、戦後のイタリアでパソリーニが詩的に表現した、ルンペンプロレタリアートと呼ばれる少年たちの、『絶望した生命力』という、生々しく、哀しく、暴力的な「美」と重なり合うことは、いまさら主張する必要はありますまい。
ロンギという人物は、カラヴァッジョとカラヴァッジョ派の展覧会のカタログを、一般の出版社からではなく、イタリア共産党の出版社から出版したのだそうです。スガルビィはロンギがコミュニストであったことから、「カラヴァッジョは(パソリーニ同様)ウルティミの画家だった。カラバッジョはバロックのコミュニストなのだ」と多少、飛躍気味に定義してもいました(ちなみに政治家スガルビィは、右派連合に属しています)。
この文脈で、アルテミジア・ジェンティレスキがカラヴァッジョとともにロベルト・ロンギ、そしてアンナ・バンティから現代に再提案されたことに大きな意味があると思うのです。この流れに連なる再登場だったからこそ、彼女が現代のフェミニズムのシンボルとして甦り、われわれ市井の者たちをときめかせるのだとも思います。アンナ・バンティもまた、精力的に美術評論、小説を上梓し、自立・独立したキャリアを築いた勇気ある女性です。
レイプという屈辱的な暴力にも、人々の好奇の目にも屈しない反発力を持ち、父親にも夫にも頼らず、独立した画家として、確固とした自分を貫いて生き抜いたアルテミジアの人生は、当時の社会を覆う価値観からすれば、奇跡とも呼べるかもしれません。
彼女の、その奇跡の人生を知って、その絵に立ち向かうなら、アルテミジアが自分の分身として描いた『ユーディット』『クレオパトラ』『ルクレツィア』『スザンナ』『オーロラ』『マッダレーナ』に重ねられた思いと、強靭な生命力が迸るのを感じます。
はるか彼方に過ぎ去った世界に生きた人物の感性とリアリティ、そしてエネルギーを、時間と空間を超えた次元で、はらわたで体感する。それこそが絵画鑑賞の醍醐味だと考える次第です。
絵画鑑賞はしたがって、かなりの体力勝負でもありましょう。