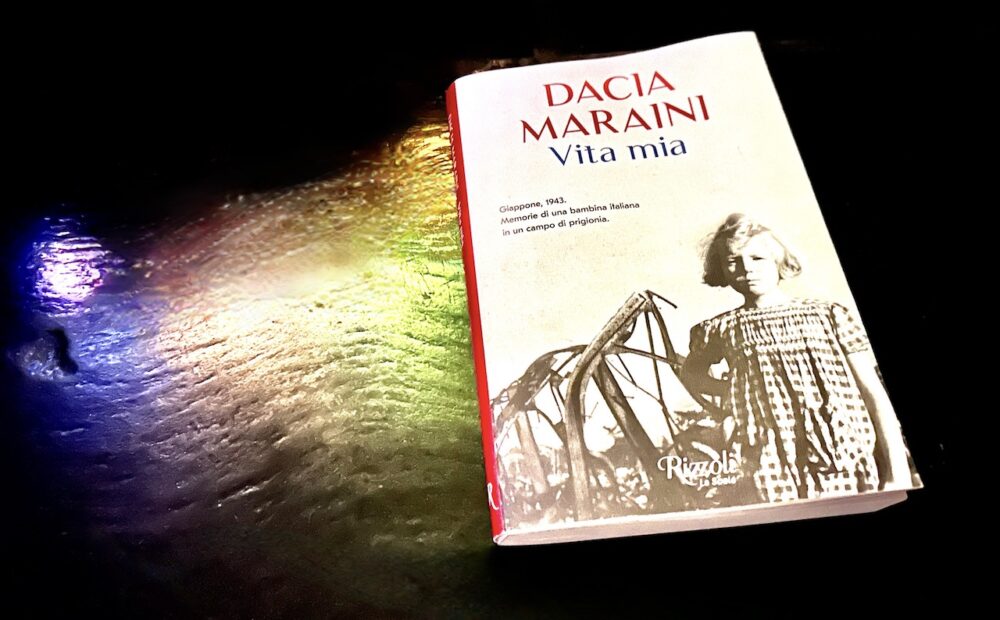飢えとサディズム
天白の捕虜収容所には、常時4人の特高警察の警官である看守がいて、ふたり1組の交代制でイタリア人たちを監視していました。その4人の容貌や性格をダーチャは克明に覚えています。
映画俳優のような顔立ちをしていたため、イタリア人たちから影で「ヴァレンティーノ」と呼ばれていた、英語を話し、多少のイタリア語も理解できる、常にきっちりとした身なりの若い看守Kasuyaは、最もサディスティックな人物だったため、イタリア人全員から憎悪されていました。
なお、戦後のKasuyaは、ダーチャの姪、ムジャ・マライーニ・メリヒのドキュメンタリーに一瞬だけ現れます(名古屋のTV局の取材による映像で)が、インタビュアーの「フォスコ・マライーニを覚えていますか」との問いに、自転車に乗った初老の男は「よく聞こえない」「わたしは年寄りだから昔のことは覚えていない。まったく覚えていない」と、逃げるように去っています。その妙に饒舌な狼狽ぶりは、ハンナ・アーレントが言った「凡庸な悪」をどことなく思い出させるシーンでした。
一方、Kasuyaとともに勤務していたNishimuraという看守は、ぼんやりとした雰囲気を漂わせていたため、イタリア人たちからはCretinetti(お馬鹿さん)と呼ばれていましたが、意外と優しい人物で、ポケットに忍ばせていた卵を1個、マライーニ家の子供たちに差し出してみたり、頭を撫で、低い声で「可哀想な子供たち」と呟くこともありました。しかしそれもやがてKasuyaの知るところとなり、その後、看守が必要以上にイタリア人たちに近づくことはできなくなったそうです。
フォスコの著作「Ore Giapponesi(随筆日本)」によると、入所当初の食事として、16人(子供たちは食事の頭数からは除外!されていました)に、1日28合の米、ひと匙ほどの味噌、醤油、少々の野菜が与えられましたが、やがてその量は、じわじわと減らされていくことになります。また子供たちは頭数に入っていないため、収容されているイタリア人たちが、それぞれスプーン一杯ずつ、子供たちに食事を分けなければならないという規則でした。このように、当初からあまりに少ない食事量のため、入所して間をおかず、イタリア人たちは全員、空腹に悩まされることになります。
別の組のAotoは、といえば、イタリア人たちから「Calogna(人でなし)」と呼ばれる、狡猾で意地悪な看守で、イタリア人たちが空腹と病で苦しんでいるのを喜ぶような人物でした。特に子供たち3人が動き回り、「お腹が空いた、ママ、お腹が空いた」と繰り返すのがうるさいようで、いつもガミガミと怒鳴っていたそうです。Aotoと組んでいたもうひとりの看守Fugijta(まま)について、フォスコは「若く、残酷で、愚かで、傲慢」、「最も粗野で軍国主義的、あちらこちらを胸を張って歩き回り、警棒を侍の刀のように持って、喚き散らしていた」と書いており、そのFugijtaは自らの厳しさを誇示しながら、大日本帝国の権威、神である天皇の威信を語っていたそうです。しかしイタリア人たちにとっては、その愚かさのため、それほど恐ろしい存在ではなかったと言います。
この捕虜収容所では、子供たちを含め、どんなに疲れていても、病んでいても、日中横になることは許されず、夜9時になるまでは、汚れた床に敷いた布団に横たわることはできませんでした。また日中に座る場合も背中を壁にもたれることは許されず、それが看守に見つかると、警棒で殴られました。
外界から完全に遮断され、常に監視され、規則を破れば警棒で殴られる収容所の中で、大人たちは当初、その鬱憤を晴らすように戦況、政治や哲学、宗教について議論していましたが、やがて時が経つにつれ、その文化的態度も変化していくことになります。次第に訪れる極限の空腹のため、食物に取り憑かれていく大人たちのなかで、トパツィアだけが静かに縫い物をし、最も穏やかで決然としていました。しかしそのトパツィアもまた、目にシミが現れ、身体の痛み、発作、脱毛が酷く、44年になると「メンタルも肉体も窒息しそう」と日記に書き残しています。
零下となる真冬には、十分な衣服、暖かい布団がないため、身体が凍え切って何度も遠い場所にあるトイレに通わなければならず、誰もが朝起き上がれないほどに疲れ切っていました。しかし38度以上の発熱がないのであれば、6時ちょうどに容赦なく叩き起こされ、それから顔を洗って服を着替え、お茶を飲んだ後、中庭を柵の中の熊のようにぐるぐる歩いて散歩をする、というのが日課で、そのすべてが決められた定刻通りに狂いなく行われ、不規則であることは許されませんでした。特にKasuyaは常に目を光らせていて、あらゆる例外を認めなかったそうです。
この「義務と忠誠」という儒教精神に起因するKasuyaの態度は、人々の苦悩、責苦を目の当たりにしながら、まったく見えないふりをする、ナチスのSSのイデオロギーを想起させるとダーチャは回想しており、イタリア人であれば、おそらくここまで規則にこだわることはなかっただろうと考えています。しかしその「義務と忠誠」の裏で、Kasuyaがイタリア人たちの食物を盗んでいたことは、トパツィアの証言から明らかであり、おそらくKasuyaは自分自身の行動の矛盾を、「裏切り者であるイタリア人を自分なりの方法で罰することは正当だ」と考えていたのかもしれません。このKasuyaという看守は、イタリア人が規則を侵すと、他の看守のように警棒で殴るのではなく、最も辛い罰である、そもそも十分には与えられていない米の量をさらに減らしたのだそうです。
このような非人間的な食事が続き、度し難い空腹に苛まれたフォスコは、看守の目を盗んでは彼らのゴミ箱をあさり、リンゴの芯、みかんの皮、魚の尾、さらに焼いた骨付き鶏肉の皮を見つけ、それらに髪の毛がへばりついていたとしても、気にせずに食べていた、とトパツィアは語っています。さらにフォスコは、ゴミ箱に捨てられた新聞を広げて読んでいましたが、それらの記事は大本営発表であったため、正確な戦況を伝えるものではありませんでした。
その頃のダーチャは、中庭で小石を見つけては、それが食べ物だと想像して匂いや味を感じる遊びに耽っていたそうです。前述したように、そもそも毎日の食事に子供たちは頭数に入っておらず、収容されているイタリア人たちが全員、スプーン一杯のご飯を子供たちに分ける、という決まりになっていましたが、やがて食事のたびに、誰もが子供たちに憎悪の視線を向けるようになり、それに気づいたフォスコとトパツィアが、「両親だけが子供たちに食事を分け与えるようにしたい」と看守に訴えても、「だめだ」と、にべもなく却下されています。
看守たちは、極限の状態にあるイタリア人たちの間で葛藤が起こることを楽しんでいたのかもしれず、「彼らは苦しまなければならない、しかし死んではならないというのが、看守たちの論理だった」のです。
そうこうするうちに、あまりの空腹に耐えられなくなったダーチャは、中庭で蟻を見つけると、次々に口に入れるようになります。それを見たフォスコが「蟻には毒、ギ酸がある。食べるんじゃない」と叫んでも、蟻を指で潰しては、咀嚼することなく夢中で飲み込み続け、ついには中毒を起こしてしまったそうです。妹のトーニはアザレアの花を食べ続け、毒にあたったこともありました。
なお、天白の捕虜収容所には3人の老人がいて、そのうちのひとりは学識が高く、とても親切なユダヤ人の教授で、日本の政治に精通した元外交官でした。その元外交官は最年長だったため、みなから「Incho」と呼ばれていましたが、子供たちを不憫に思って、ずっと隠し続けていた桃のシロップ漬けをプレゼントしてくれたこともあったそうです。その他の人々は、横浜で商売をしていた人物や、日本の歴史、宗教をよく知る宣教師、エンジニア、フィアットの東京代表、フリウリの農業に携わる人物、ローマの元学生で、さらにはそもそものフォスコの友人であったジョルジョとソーニなど、若いイタリア人が7人いて、そのうちのひとり、当時30歳だったフォスコも含め、その若い7人が料理、収容所の掃除を請け負っています。
収容所に連行されてしばらくは仲良く、互いを思いあって過ごしていた彼らも、寒さによる病と栄養失調の腹いせか、やがて貝杓子を振り回しての喧嘩や衝突が起こりはじめることになりました。それでも、収容所内では民主的な討論は保たれていたようで、「(われわれの)グループは、政治、歴史、宗教、美学をテーマとした議論で取っ組み合いをするが、実際のところは気高く、団結した20世紀の欧州の文化人により構築されており、敵対する世界で、理性という帝国の下、障害を克服しようと決意していた」とフォスコは書いています。
▶︎フォスコの叛乱