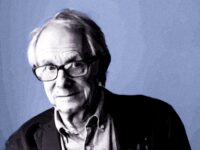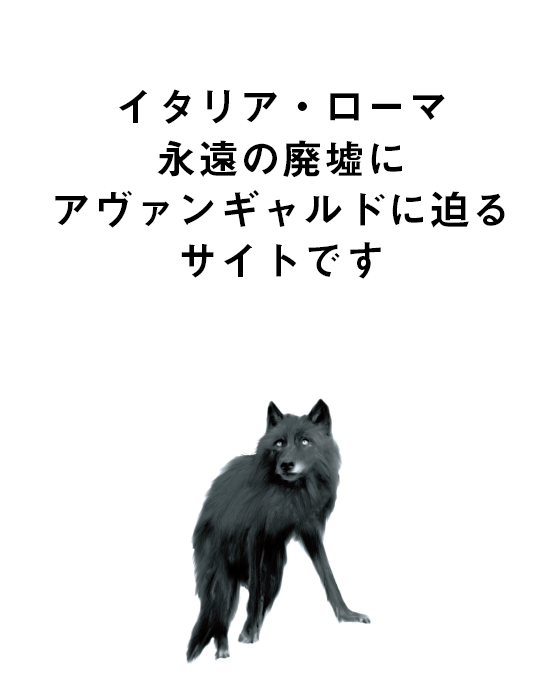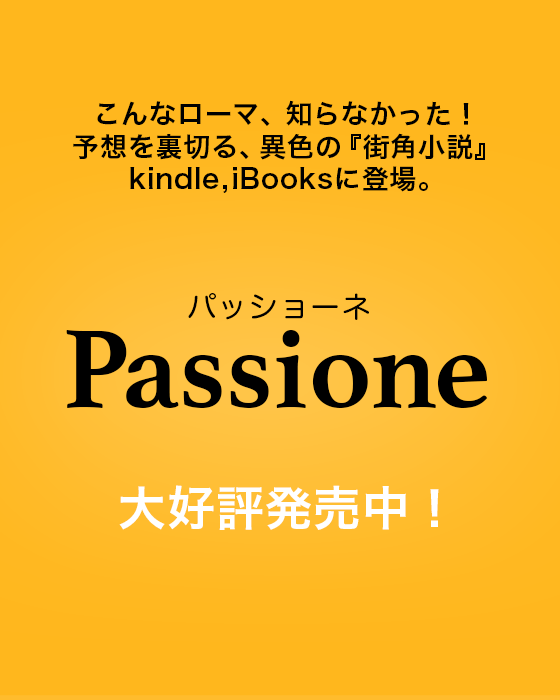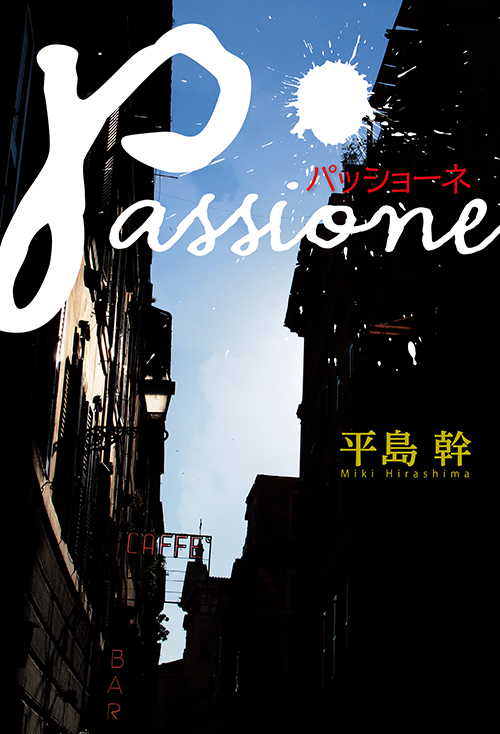合法と違法の狭間で
では話を私が住んでいたローマに移したい。ローマにも多数のグラフィティがあり、どれもなかなか魅力的だ。グラフィティに誘われるようにローマの各所をふらふらと見学していて、作品のテーマや内容とは別に、グラフィティが2種類に分類できることがわかってきた。合法のものと違法のものだ。私がよく通ったのはピニェートからトル・ピニャッターラにかけての町の南東の地域で、こちらも地域のジェントリフィケーションを目的に多くのグラフィティが点在している。
特にポーランドのエタム・クルー(Etam Cru)というユニットが描いたゴミ箱から顔を出してコーヒーを飲む男のグラフィティ「コーヒーブレイク」は、その大きさがなんと32メートルもあり見ごたえ抜群だ。題材も絵のタッチも面白いが、こういったグラフィティは概ね「合法」である。行政の許可がないとこのような大きなグラフィティは描けないし、依頼を受けた名のあるアーティストが落ち着いた環境で描かないことには、斬新な題材も精巧なタッチも成立しない。
いっぽう「違法」のグラフィティは一般的に合法グラフィティほどスケールが大きくもなければ、芸術性にも乏しい。本来描いてはいけない壁や地下鉄の車両などに、書きなぐられている。差別的だったり、特定の政治家や著名人を蔑んだりといった内容のものも散見する。時間をかけて描かれたスローアップやイラスト風のグラフィティでも、合法グラフィティにみるような絵画的要素は乏しく、ポップアートに近いものが多く、場合によっては景観を乱しているとも捉えられかねない。
これら違法グラフィティは、常に消されてしまう可能性と隣り合わせにあるのが特徴だ。例を挙げるとローマのピラミデにある高架下だ。2025年はカトリックの聖年で、ローマ市内を整備しようという動きが強く、違法グラフィティの宝庫だったポルト・フルヴィアーレの高架下に先日行ってみたところ、きれいさっぱり塗り直されていた。ただ、塗り直された壁の上に、新たに雑草が生えるように、すでにグラフィティがいくつか描かれいた。このようなカオスないたちごっこがあちこちで展開されているのが違法グラフィティの世界だ。
もう一つ例に挙げたいのが、この高架下の真横にある旧航空兵舎だ。長期にわたり閉鎖されたままだったこの建物は、2003年から不法占拠がはじまり、いちばん多い時期で160世帯が住んでいた。この建物には、窓の部分を目に模した色とりどりの顔が壁一面に描かれていた。Bluという覆面ストリートアーティストが描いたこの作品は、ローマでもっとも特徴的な作品の一つだった。それが先日訪れたときには、都市整備のために工事中になっており、作業用のシートで隠されグラフィティが見えない状態になっていた。整備後も作品を残すという話もあるが、具体的にはどのような形になるかわかっていない。
このように違法グラフィティは、いつなくなってしまうかわからない儚さ、危うさを孕んでおり、それがまた独特な魅力になっているように思う。
ジェーコのGECO
旧航空兵舎が不法占拠されていたと聞くと何やら物騒な印象を抱くかもしれないが、実はローマには不法占拠されている建物がその他にもいくつかある。もとは精肉工場だった住居兼ストリートアートの美術館MAAM(il Museo dell’Altro e dell’Altrove)や、ローマ各地にある社会センター(Centro Sociale)と呼ばれるイベントスペースの数々など、詳しく紹介するのは別の機会にするとして、ぎゅっとまとめるとこういうことになる。ローマ、そしてイタリアには不法占拠され、それが公認となった場所が多数あり、違法なのか合法なのかあやふやな空間で、地域のアンダーグラウンド・カルチャーが醸成されている。そして、そういった空間はグラフィティともまた非常に相性がよく、新たなグラフィティもまた、そういった環境から生まれている。
だが、最後に紹介したいのは、数あるグラフィティのなかでも特殊中の特殊な存在で、その違法性から「イタリアのバンクシー」と呼ばれているジェーコのグラフィティだ。イタリア語のスペルでGECOはヤモリという意味だ。彼が描くのは、基本的にGECOの4文字のみ。通常は誰も描かないような建物の高所に描く「ヘブンスポット」の名手で、作品の大きさ、量、スタイルのどれをとっても他の追随を許さない。
もちろんどの作品も違法であり、彼自身匿名で活動していたが、2020年に警察の捜査で本人が特定されて逮捕されてしまった。ジェーコ逮捕のニュースで改めて巻き起こったのが、グラフィティはアートなのかという論争だ。すでにグラフィティが景観を乱しているとも捉えかねないと書いたが、ジェーコの場合はさらに質が悪くて、建物への不法侵入、器物破損、多額の賠償金まで関わってくる。芸術性という観点からも、絵画的な要素は皆無で、むしろ町中をジェーコのグラフィティで蔓延させるという行為自体が「アートかどうか」の論点となる。
そんなことを考えていたら2025年、ジェーコのドキュメンタリー映画が公開された。これは青天の霹靂だった。その名も”The art of disobedience”。邦訳するなら「不服従のアート」だ。監督はジェーコ自身で、映画のクレジットによると編集もジェーコが担当している。内容はジェーコが時に住民に「通報するぞ」と警告を受けながら、実際にグラフィティを描く様子が克明に記録されている。この映像は誰がどうやって撮ったの? ずっとカメラを回していたの? 逮捕されたのにいつ編集したの? などなど、鑑賞しながら頭に疑問符が駆け巡る映画だったが、社会的規範を外れることで表現の自由や芸術の本質を問うことが彼のグラフィティのポリシーであることはよくわかった。
そして私のグラフィティに対する価値観は大きく変わった。つまり、いっぽうでヨーリットやエタム・クルーのグラフィティを芸術として持ち上げ、都市整備のツールとして利用するくせに、ジェーコのグラフィティは違法行為だとして逮捕する。結局は一般的な規範の枠内に収まったものしか作品として受け止められていないのではないか、それは本当の意味で芸術と向き合えていないのではないか。”The art of disobedience”にそんな問いを突き付けられている気がした。ジェーコからもう一度グラフィティについて考え直していきたいと思いつつ、本稿の筆をおくことにしたい。