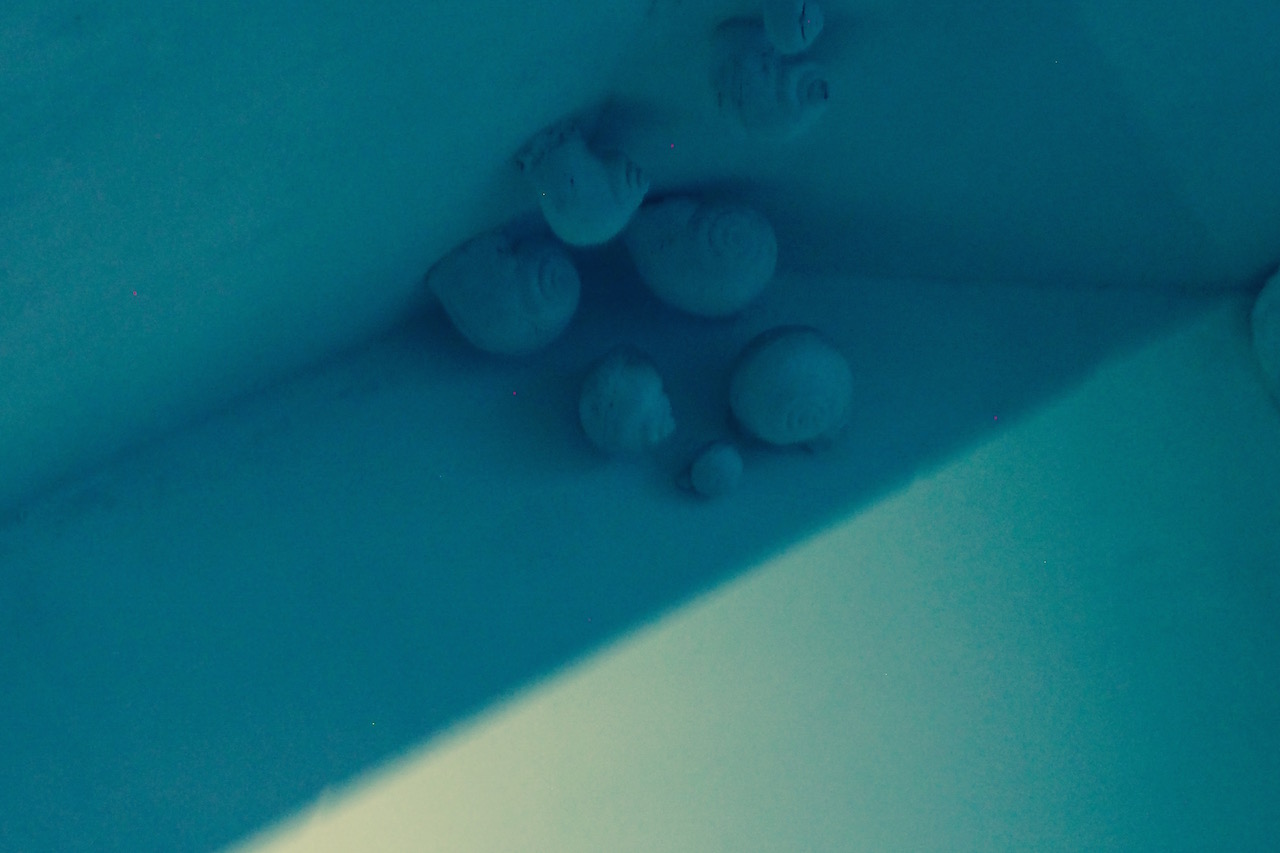さて、このドキュメンタリーに参加したアーティストたちは、撮影後も増え続け、前述したように、現在では450人にも上っています。そのなかにはLuigi Ontani(ルイジ・オンターニ)、Michelangero Pistoletto(ミケランジェロ・ピストレット)などのイタリア美術界の巨匠、Gian Maria Tossatti(ジャン・マリア・トッサッティ)、Franco Losvizzero(フランコ・ロスヴィッゼロ)、Veronica Montanino(ヴェロニカ・モンタニ)、Mauro Cuppone(マウロ・クッポーネ)と、現代イタリア美術を代表するアーティストたちも含まれます。彼らは作品を創作する間、このスペースで『占拠者』たちと共に過ごしています。ヴェトナム戦争に作品で抗議したことで有名な、アルテ・ポーヴェラ・ムーブメントの最重要アーティストのひとりであるミケランジェロ・ピストレットは、4ヶ月もの間、このスペースに滞在したそうです。
また、ローマのストリートアートで注目されるLucameleonte やイエメンから亡命してきたアーティスト、アラブ人でありながらアナーキストのAladin(アラディン)も参加。Aladinは、「神の存在を信じない」と公言したことで、イエメン政府から死刑を宣告され、ローマに亡命してきたと言います。ドキュメンタリーフィルムでは「時代が変わって、僕の想像していたフェリーニのローマはなかった。それにイタリアにはイエメンとは違う問題が、多くあることもわかってきたよ。アラブ世界には「占拠」なんてありえないけれど、僕はこのような共生は好ましく思っている」という趣旨のことを話しています。
もちろんMetropolizは、それでも不法占拠ですから、今までも何度となく強制退去の危機に直面していますが、当局も数多くのアーティストたちが残した、アート市場的にも価値のある、つまり10万ユーロを超える値がつく作品を含むアートスペースを無闇に破壊するわけにもいかず、常に緊張を孕むギリギリのスタンスではありながらも、いまのところ、その作品群に守られて、人々は平和な日々を送っています。なお、アーティストたちは材料費も含めて、すべて無償で作品をMetropolizに寄贈。それが現在のMAAM、この特殊な現代美術館の基礎となっているわけです。
ところで、わたしがMetropolizに行った日、ちょうどファブリッツィオ・ボーニとジョルジョ・デ・フェニスが先ごろ出版した本、『SPECE METRO-POLIZ』のプレゼンテーションが開かれていました。そのプレゼンテーションに参加し、本を購入したところ、そのなかにレナート・ニコリーニの評論を発見。70年代、ローマの街にヴァイオレンス・カルトが吹き荒れ、恐怖と悲しみが覆った『鉛の時代』を、Estate Romana(ローマの夏)というおおらかで、のびのびとしたイベントで、街の空気を一新、その後のローマの文化の流れを決定づけた建築家、そして政治家でもあった彼は、Metropolizにも一文を寄せていました。ローマのすべての市民にが分け隔てなく、自由に交流できるTeatro Sociale(社会的な劇場)を創出し、公共スペースを市民で平等に分かち合うことをめざしたこの知識人は、この映画が完成した2012年に、多くの人々に惜しまれながら亡くなっていますから、彼の生涯の最期に近い時期に書かれた文章に違いありません。かなり長い文章なので、ところどころ略しながら意訳引用したいと思います。
François(フランソワ)のロケット、ユートピアとディストピアの間。
ユートピアは一体どこにあるんだ?
ユートピアは、しかしこの言葉が持つそもそもの意味から考えるならーOu (non 否定) Topos(luogo 場所)ー現実のあらゆる場所に存在しようがないのだ。突然、社会、経済、文化の状況が大変動、既存の制度が激震を起こしても、あらゆる場所が、どのような場所にも置き換わりえないのと同じように、この場所、存在の不可能こそが、ユートピアの普遍たる所以である。しかしポストモダン、ポストイデオロギー、ポストメトロポリタンのわれわれが生きる文明において、この考え(本質的にはフランス革命ー時代の先駆けとなったーに強く結びついた啓蒙主義的な)は、多分もはや真実ではない。ユートピアの普遍、ポストユートピアは、成熟すら超越してしまった資本主義の傾向(堕落した)を、まったく拒否した「ディストピア」にとって代わられた。Marc Augè ( フランス人異民族学者、文化人類学者)の理論によると、ポストユートピアは大抵、メトロポリスの郊外、常にラディカルな変化のあるトポスなき世界に簡単に見つけることができるというのだ。
ディストピアに魅入られた場所・・・。この見えない場所の存在は、有名なラカンのエドガー・アラン・ポーの「盗まれた手紙」に関する理論と同じかもしれない。隠されたものは、存在する場を持たない。その場所にアクセスすることはできないが、目には見える、つまり完全に目に見える場所に隠された『盗まれた手紙』のように。ただ、この話は完全に逆転する・・・Metropolizの隠された住居は、彼らにとっては外界であり、また、外界が彼らにとっての住居でもあるのだから。
ある土曜の朝、ジョルジョ・デ・フィニスとマッティア・ペッレグリーニに誘われて、僕はついにMetropolizにやってきた。長い間、そもそもフィオルッチのサラミ工場だったという理由から、僕の好奇心をそそった場所だ。Metropolizの存在は、スイス人の建築家Gioachino Ersochによる「死のための機械」、テスタッチョの「屠殺場」を想起させたからだ(現代美術館MACROは、家畜の屠殺場が、その形状、施設を残しながらスーパーモダンに改装され、ローマ市の重要な美術館のひとつとなっています)。
サラミメーカーのフィオルッチは、60年代、70年代のはじめに、チェントチェッレの”ドン・クリスチオッテ”として、キリスト教民主党でキャリアを積み、老人となっても相談役としてローマ市政に関わった人物だが、そんな状況(産業の発展により好景気に恵まれた時代)は、もはや跡形もなく消えた、遠い昔の話だ。そのころのローマはいまや存在しない。ローマが世界でも魅力的な街だった最期の残り火はオードリー・ヘプバーンが街にまぎれて「ローマの休日」に隠れることができたころ、あるいはオーソン・ウェールズが、オセロを撮る予算が降りるのをフラスカーティで待ちながら、撮影チームをシャンパンでもてなすことができたころだ。
一方、存在するのは、Invisibilita(不可視)であることが強いられてはいても、古くから残った街のあらゆるものを、疲弊しながらも、なんとか循環させようとする新しいローマ、移り気なアイデンティティの新しい形を探そうとしているローマだ。フィオルッチのサラミ工場は、住居としてMetropolizとなり、カンピドリオ(ローマ市庁のある)からは無視されたまま、さまざまな人種が「占拠」により共生する場所になった。しかもその場所には、通常のイタリア人家族に嫌がられ、ローマ環状線内にはなかなか住居を得られないロムのグループも共生しているというのだ。
Stalker(ノマド生活を観察する建築家グループ)による、低コストの実験的住居の提案がヴェネチア建築ビエンナーレに受け入れなかったのち、「僕らがここにいることが許されないのなら、どこに行けばいいんだ。月にでも行くしかないじゃないか」ということになった。
この『月へ行く』というコンセプトは、George MèLiésの映画のロケットから着想を得たもので、月は常に多くの詩人たちの最も偉大なシンボルともなっている。中国の李白の詩にも「月を指差すと、見てごらん、指は歪んでいる」とある・・・。こうしてMetropolizのアート作品は、月というサインのもとに創作されることになった。月には人間が失った思慮、知恵がある、とルードヴィコ・アリオストが言ったように、Metropolizは本来ならローマの公共財産として、解決すべきでありながら、すっかり失われたその思慮を実現した場所でもある。
遠くからこの場所を見ると、Hogreがデザインした塔がまず最初に見え、矢印が空を指し、人が月へ向かう。その頂上にGian Mario Tosatti(ジャン・マリオ・トッサッティ)が創った天体望遠鏡が設置されてある。塔は、もし強制退去で当局がなだれ込んできた場合、占拠者たちの最期の逃げ場でもあり、当局からの警告は、いまだ停止することはない。入り口の部分にあるSten&Lexのグラフィティは「月の人々へ」と献辞され、Fabio Pennacchia(ファビオ・ペンナッキア)は月の菜園を創った。Casa dell’Architettura(建築の家ーローマ市営建築会館)にアーカイブされているストリートアーティストLucameleonteが、食堂の一面の壁を50年代SF雑誌のパルプな表紙に描かれるようなタッチで「宇宙への楽しい冒険」と題して、月の住民と植民地支配する者たちの闘いを描いている。またイエメンからの亡命者、Aladin(どうやら彼のいた北イエメンで、彼は大臣の右腕にまでなった人物らしいが)は月の上のMetropolizを描いた。
そしてどうして今、僕がMetropolizに関する、こんなメモをとっているかというと、実はこのMetropolizで、僕の幼きころの友人、Maurizzio Françoisーマウリッツィオ・フランソワのロケットをついに見つけた、と感じたからだ。それは小学二年生のころの話だ。クラスの友達であるマウリッツィオは、いつも電話で、僕に何かよくわからない騒音を聴かせてくれた (そのころ母は、僕を彼の家に遊びに行かせてくれなかったのだが):マウリッツィオは「今、月に行くためのロケットを創っているところなんだ!これがその音だよ。創り終わったら、一緒に月に行こう!」そう僕に言い続けた。
それからの僕といえば、マウリッツィオの言う月のことばかりを考え、毎日熱望し、と同時に信じられない気持ちでいっぱいだった。ある日のこと、ようやく母親から彼の家に出かけてもいいと言われ、僕は興奮してそれをマウリッツィオに学校で伝えることが実現した。僕はいよいよ月に行く、という現実に胸を膨らませながら、その日の夕方、家を出るまえに彼に電話をかけると(僕らはその日のうちに月に出発することにしていたので)いつもの騒音がしない・・・。「お手伝いさんが捨てちゃったんだ!」彼は残念そうに言った。
ほら、僕はあのマウリッツオ・フランソワのロケットを、遂にMetropolizで見つけた! アルド・ロッシ(建築家)の世界劇場のなかに(1980年のヴェネチア・建築ビエンナーレのインスタレーション)、Mèliésのスケッチのなかにある、先が丸い、丸い重りのついた、あのロケットを。そしてそれを飛ばすには、ただ子供の気持ちに戻るだけでいいんだ。
1日中、スペースを散策して、すっかり暗闇に包まれる時間、案内をしてくださったカルロ・ゴーリとともに乗った帰りのバスで乗り合わせた、Metropolizの住人であるイタリア人の婦人と話すうち「Metropolizは素晴らしい場所なんだよ。悪口を言ったら許さないからね!」と念を押されました。そういうわけで、今回の項を、細心の注意を払って書いてみましたが、実際のところ、批判するような部分も見つからず、荒れ果て趣、少し下水と、カビ臭さのリアリティで、より深みのあるVita(生命)を感じました。「生きて、呼吸して、老いていく」芸術作品に守られた、無秩序ながらハーモニーのある、いままで知らなかったアートスペースへの冒険の旅に、相変わらず不思議な、しかし温かい気持ちで、帰路についたことを付け加えておきたいと思います。